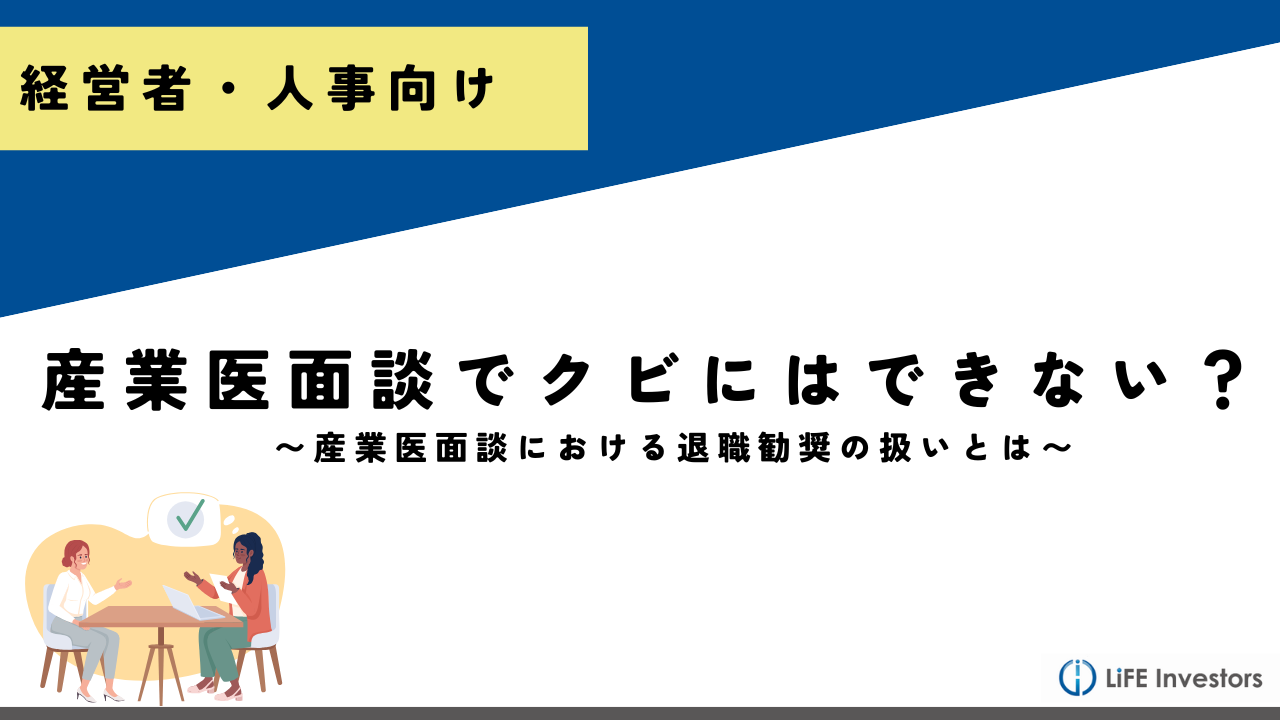この記事はこのような方に向けて書いています。
・産業医から休職中の従業員やメンタルヘルスに不調を抱えている従業員に対して退職勧奨を行うことは可能なのか知りたい方
・産業医を通して企業側からクビにされようとしているのではないかと感じている従業員がいて対応に困っている人事担当者の方
様々な事情により休職している人やメンタルヘルスに不調をきたしている方にとってクビにされるのではないかという不安は常に付きまとうものです。このような状況にいる従業員の心情を理解し、適切に対応することは、企業や産業医にとって極めて重要な課題と言えます。特に、産業医面談の場では、この不安を必要以上に煽ることなく、従業員が安心して話せる環境を整えることが求められます。
本記事では、産業医面談において退職勧奨をどのように取り扱うべきか、また従業員からクレームが発生しうる状況とその対処法について詳しく解説します。
産業医面談とは
産業医面談とは従業員の健康をサポートするために行われる取り組みです。産業医は医学的な専門知識をもとに従業員に対して助言を行い、健康管理や職場環境の改善を支援します。
特に、長時間労働を行っている従業員に対しては、産業医による面接指導が法律で義務付けられており、以下のようなケースで実施されます。
- 体調の悪化を未然に防ぐため:従業員の健康状態を把握し、必要に応じて労働時間の調整や業務負担軽減の措置を講じる。
- 職場環境の改善ポイントを明らかにするため:作業環境の問題点を分析し、解決策を提案する。
- 医学的な指導が必要と判断される場合:従業員に健康維持や改善のための具体的な助言を行う。
産業医の守秘義務と報告義務について
産業医には、従業員のプライバシーを保護する「守秘義務」と、企業や関係機関に必要な情報を伝える「報告義務」が課されています。
守秘義務
産業医は、職務を通じて知り得た労働者の情報を、正当な理由なく第三者に漏らしてはなりません。この義務は以下の法律で定められています。
- 労働安全衛生法 第105条
- 刑法 第134条(秘密漏示罪)
(健康診断等に関する秘密の保持) 第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
労働安全衛生法第105条
(秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法134条
報告義務
一方で、従業員の健康状態が職場全体に影響を及ぼす可能性がある場合、必要な範囲で企業や関係者に報告を行うことが求められます。ただし、この報告は従業員の同意を得たうえで行われ、プライバシー保護にも十分に配慮する必要があります。
基本的には守秘義務が優先されるため、事業者への報告は原則として従業員の同意を得て行います。 しかし、刑法第134条に基づき、正当な理由がある場合には本人の同意なく報告することも可能です。
本人の同意なしで報告できる正当な理由は
- 法令に基づく場合
- 第三者の利益を保護するために秘密を開示する必要がある場合
- 患者や他者に対して現実に差し迫って危害が及ぶおそれがあり、守秘義務を優先すると危険を回避できない場合
などです。
具体的には、
- 労働者に自殺のリスクがある場合
- 就業制限が必要とされる感染症や伝染病にかかり、周囲に感染を広げる可能性がある場合
- 現状の労働環境のまま働くと病状が悪化する恐れがある場合
などです。
たとえ正当な理由があったとしても情報の開示は労働者本人の感情に影響を与え、トラブルに発展する可能性もあるため、慎重な対応が求められます。具体的には、以下のポイントに留意することが重要です。
- 事前に同意を得る:情報を開示する際は、可能な限り従業員本人の同意を得る。
- アフターフォローを徹底する:開示後は、その理由や必要性を丁寧に説明し、本人が納得できるよう配慮する。
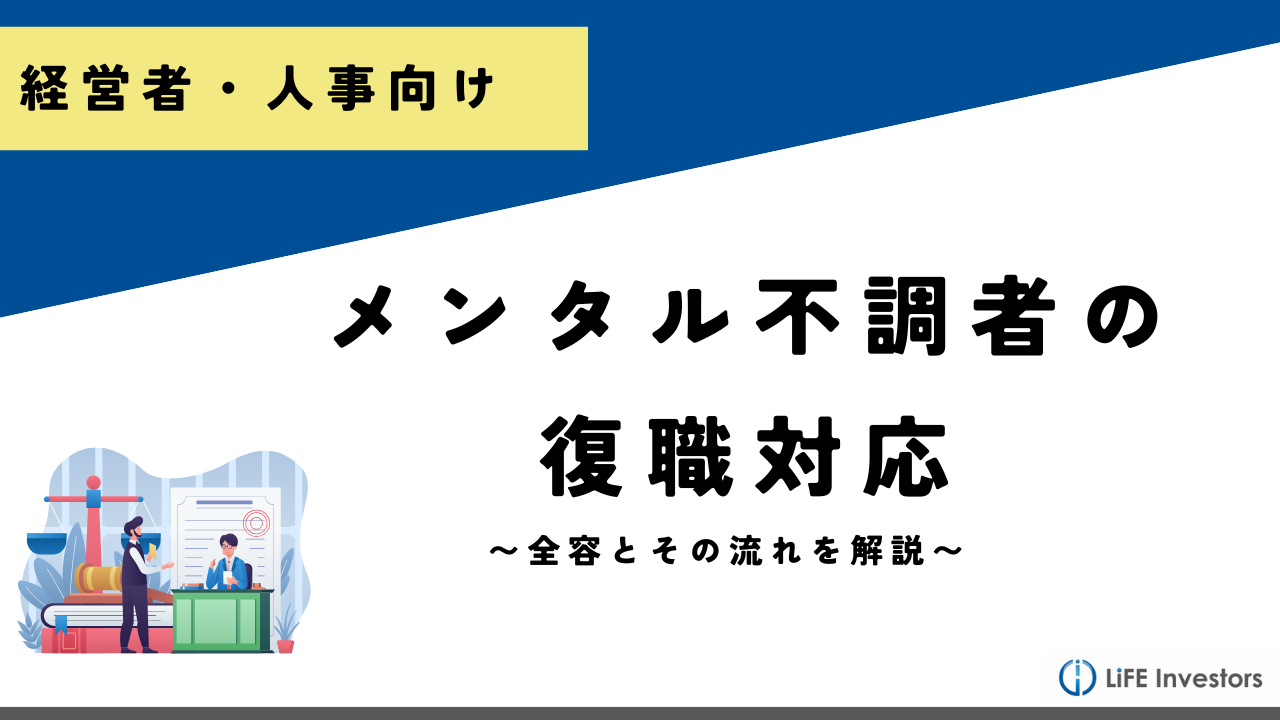
産業医面談で退職勧奨することは可能なのか
メンタルヘルスの不調や身体的な病気、その他の事情により長期間休職している、または復職後も遅刻や欠勤を繰り返している従業員への対応に悩む人事担当者は少なくありません。特に、復職後の遅刻や欠勤が重なる場合、欠員が生じるタイミングが予測しづらく、マネジメントに支障をきたすケースもあります。
このような状況で、「産業医から退職を勧めてもらえば、直接伝えるよりも角が立たないのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、結論から言うと産業医面談で退職勧奨を行うことはできません。産業医の役割は、あくまで従業員の健康を管理し、職場環境の改善を支援することであり、退職勧奨は企業側の人事部門や経営陣が判断・対応すべきものです。そのため、産業医が退職勧奨を代行することは適切ではありません。
産業医に認められている「勧告権」とは?
産業医には、労働安全衛生法第13条5項に基づき、「勧告権」が認められています。
5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
この権限は従業員の健康を守り、職場の適切な就業環境を整えるために用いられます。そのため、健康維持のために勤務時間を調整するなどの就業制限をかけることはできますが、退職を促すことはできません。
退職勧奨は、産業医の役割を超えた行為であり、法的にも認められていません。 産業医は中立的な立場を維持する必要があり、退職の判断は企業と従業員の間で行われるべきものであることを念頭に置いておきましょう。
ただし、企業と従業員の間で「休職期間満了までに復職できない場合は雇用契約を終了する」と合意している場合、産業医が復職許可を出さないことで結果的に退職につながるケースもあります。 しかし、これはあくまで産業医が従業員の健康を守るために適切な判断をした結果であり、退職を目的としたものではありません。
また、産業医との面談を通じて、従業員自身が健康面を考慮し、退職を決断するケースもあります。
従業員が産業医面談で退職を促されたと感じる瞬間とは
では従業員はどのような時に退職を促されたと感じるのでしょうか。
転職の話をされた時
産業医との面談で転職の話が出ると、「仕事を辞めろ」と遠回しに言われているのではないかと感じる従業員もいます。しかし、多くの場合、産業医は従業員の健康状態を考慮し、適切な対応を判断する材料として意思確認をしている可能性が高いです。
誤解を防ぐためには、質問の意図を明確に伝え、従業員が目的を理解できるようにすることが重要です。特に、具体的な意図がないまま質問するのは避けたほうがよいでしょう。
仕事があっていないのではないかと言われた時
この発言は、「仕事が合っていない(=辞めるべき)」と受け取られる可能性があります。転職の話と同様に、意思確認の目的で発言する場合は、質問の意図を明確に示すことで誤解を防ぐことができます。
復職を希望しているのに復職許可をもらえない時
就業規則に定められた休職可能期間が迫る中で復職を希望しているのに復職許可が下りない場合、従業員は「間接的に退職を促されている」と感じることがあります。この場合、復職許可を出せないのはまだ十分に体調が回復していないからですが、休職可能期間の満了期限が迫って気持ちが焦っていると産業医を敵視してしまいがちです。復職許可を出せない理由を丁寧に説明し、従業員から理解を得られるように努めましょう。また、必要に応じて主治医と連携し、情報提供依頼書を提出するなどの対応も検討しましょう。
退職を勧められた時
産業医が直接的に退職を勧めることは法的に認められていません。 このような状況が発生しないよう、十分に注意が必要です。
従業員から産業医に対するクレームが出た時にとるべき対応とは
従業員から「産業医の先生に退職を勧められた」「クビにするぞと言われた」というクレームが来た場合はどのような対応を取ればいいのでしょうか。
産業医に事実確認をする
「産業医から退職を勧められた」「クビにすると言われた」といったクレームが寄せられた場合、まずは産業医に対して事実確認を行うことが重要です。
産業医側に非があるケース
産業医が勢いで不適切な発言をしてしまった場合は、改善を求めるか、必要に応じて産業医の変更を検討しましょう。
従業員側の誤解によるケース
産業医が適切に対応していても、従業員がナーバスになり、圧力を感じてしまうこともあります。この場合は、丁寧なフォローを行い、誤解を解くことが必要です。
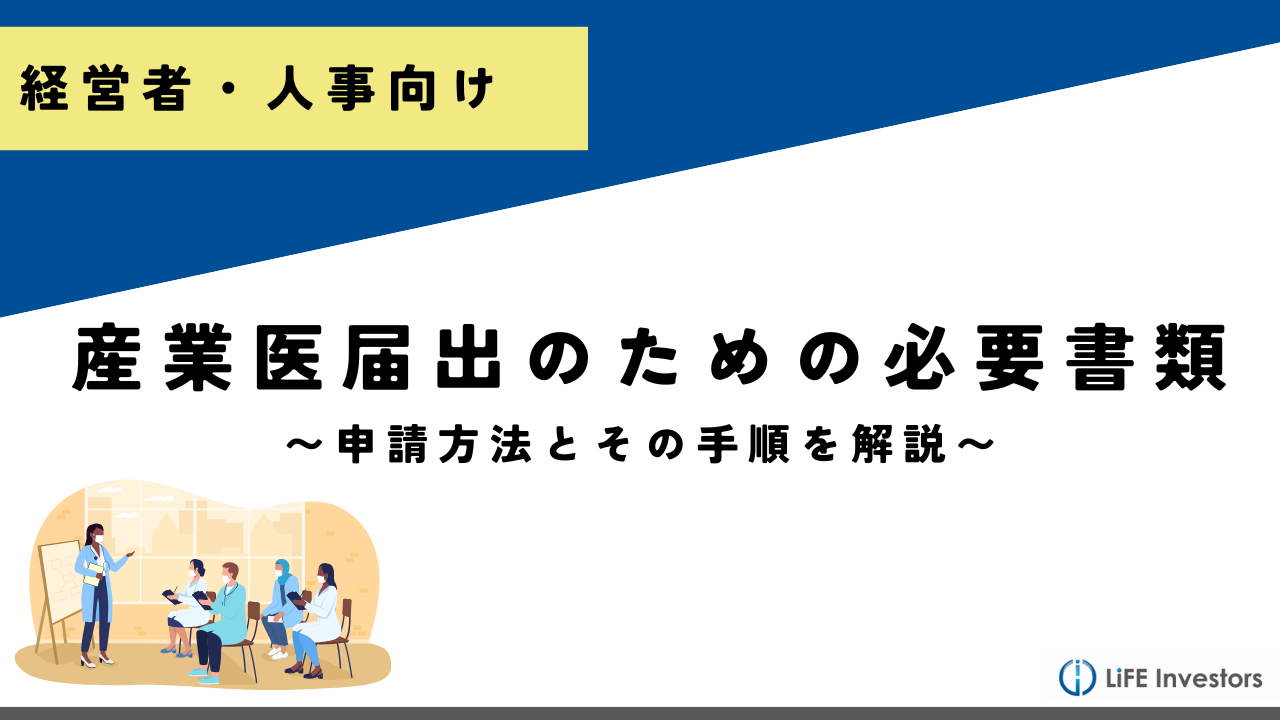
産業医面談に第三者を立ち会わせる
産業医と従業員の面談では、従業員が過度に緊張したり、圧迫面接のように感じてしまうことがあります。そのため、直属の上司や人事担当者などの第三者を面談に立ち会わせることで、産業医面談の透明性を高めることができます。ただし、プライバシー保護の観点から、従業員の同意を得た場合に限ることが望ましいでしょう。
まとめ
ここまで産業医面談における退職勧奨の問題やクレームが発生した際の適切な対応について解説しました。仕事を続けるかどうかは、従業員の今後の人生に大きく関わる重要な問題です。 そのため、この問題に取り組む際には慎重な対応が求められます。
産業医や企業側は、従業員がどのように感じているかを理解し、意図を正しく伝えることが重要なポイントとなります。 また、産業医・従業員・企業それぞれの立場や役割、権限を改めて確認し、不必要なトラブルを防ぐことも大切です。
適切な対応を心がけることで、従業員が安心して働ける職場環境の維持につながります。
ライフインベスターズでは、コミュニケーション能力や専門性など、書類や面接審査を通じて一定の基準を満たした厳選した産業医が所属しております。
大手法人様はもちろん、これから衛生委員会を立ち上げるスタートアップ・ベンチャー企業様への対応経験も豊富にございます。特にメンタル対応についてお困りの法人様から専門性の高さで高くご評価いただいておりますので、産業医の交代を含め、何かお困りやご不満がございましたら、無料のオンライン相談も受けつけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
【参考文献】