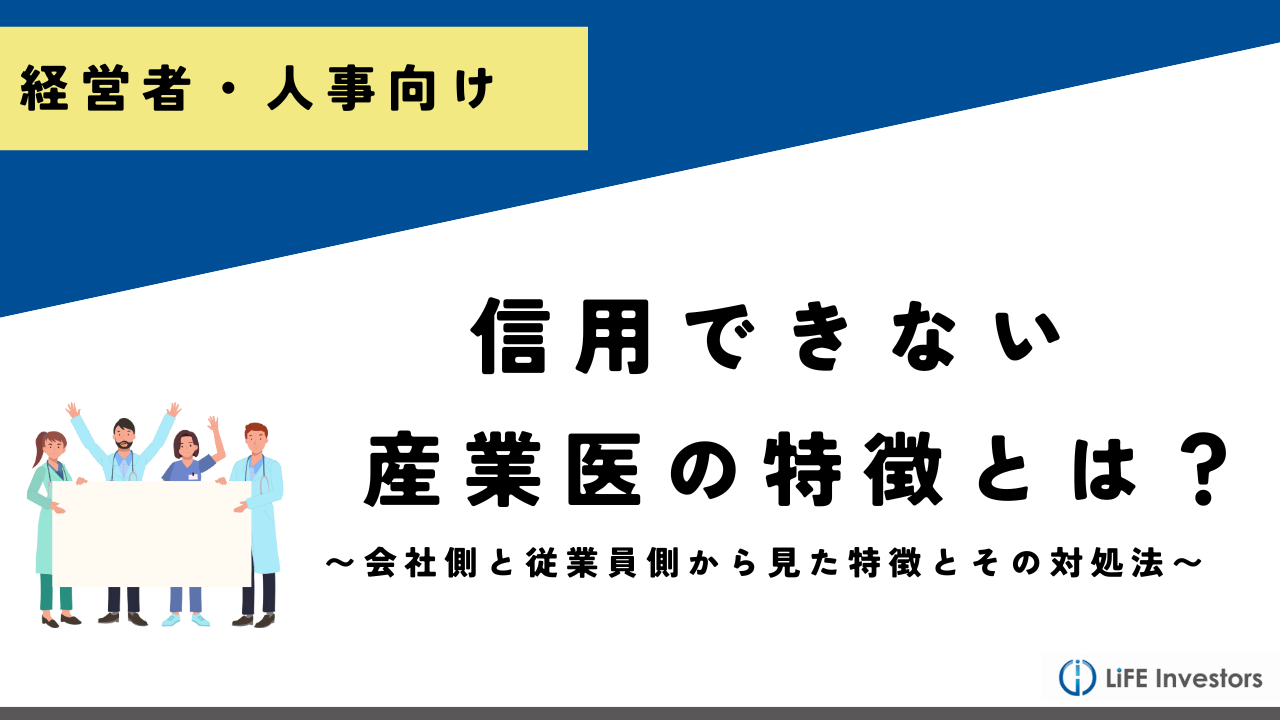この記事はこのような方に向けて書いています
・産業医が予定通り働いてくれずに困っている人事・労務担当者の方
・悩みを抱えて産業医に相談するべきか迷っている従業員の方
「産業医を契約しているのに、スケジュール変更が多すぎる」「上から目線で話され、相談しづらい」など、不満を抱いたことはありませんか?こうした不信感が積み重なると、企業としての健康管理体制や労務リスクにも影響が出かねません。
私たちのもとには、産業医との関係に課題を感じている人事・労務担当者から「新たな産業医を探したい」「信頼できる産業医に切り替えたい」といった相談が寄せられています。
そこでこの記事では、企業側と従業員側の視点から見た「信用できない産業医」の特徴と対処法を解説します。また、最後には「信用できない産業医」を見分けるためのチェックリストもご用意しました。
ぜひ読み進めていただき、現在の産業医が適切かどうか、確認してみてください。
また、産業医をどう活用したらいいのか、産業医と契約したいなどふとした疑問で知りたい場合はどうぞお気軽に問い合わせください
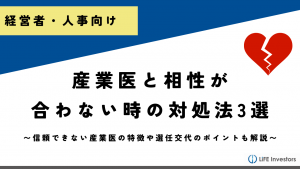
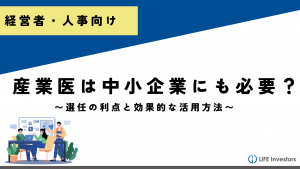
そもそも信用できない産業医とは?
産業医は法律や倫理に基づき、企業と従業員の健康管理を担う役割があります。しかし「信用できない産業医」は、その役割を果たさず、企業や従業員に悪影響を与えることがあります。
例えば、法律的には以下のような産業医が問題視されます:
- 法律(安全衛生法など)で定められた業務を怠り、不当な行為に加担する産業医
また、企業と従業員それぞれの目線から見ると、次のような理想を産業医に抱くケースがあります:
- 企業目線:自社の意向を完全に受け入れる産業医が望ましい
- 従業員目線:いつでも従業員の味方になってくれる産業医が理想
しかし、このような極端な期待を産業医に寄せるのは、短期的には良い結果を生むこともありますが、長期的にはリスクが伴います。産業医は中立的な立場で双方のバランスを取りつつ、法律や倫理に基づいた行動をすることが求められます。
以下では、企業と従業員、それぞれの目線から「信用できない産業医」の特徴について詳しく見ていきます。
弱者の味方?会社から見た信用できない産業医の特徴
- 会社側に情報を共有しない
- 主治医の意見をそのまま鵜呑みにする
- 虚偽の主張を行う
1.会社側に情報を共有しない
「個人情報だから」という理由で、従業員に関する情報を企業に共有しない産業医は少なくありません。例えば、産業医が従業員と面談をしても、結果が報告されないままでは、企業側はどう対応して良いかわからず、混乱してしまいます。
もちろん、従業員のプライバシーを保護することは大切です。しかし、企業側も従業員の復職や職場での適応を支援するためには、一定の情報が必要です。情報不足のままでは、的確な対応が取れず、問題が長引いてしまうこともあります。
たとえばこんなケースが…
ある企業で、精神疾患を抱えた従業員が産業医と面談をしました。ところが、面談結果について企業への共有が一切なく、復職時期や必要な配慮について何も知らされないまま。結果として、企業側が対応を誤り、従業員の状態が悪化。職場全体の士気も低下してしまいました。
産業医は、従業員と企業をつなぐ「架け橋」となるべき存在です。必要な情報は適切に共有し、企業が従業員の支援に集中できるようサポートすることが求められます。
つまり、産業医も社員同様当たり前の報連相ができることが非常に重要となります。
2.主治医の意見をそのまま鵜呑みにする
「主治医が復職可能と言っているので、復職させましょう」と、企業の事情を無視して判断を下す産業医もいます。しかし、主治医の役割は日常生活の回復度合いを見ることであり、職場環境や業務遂行能力の評価は産業医の重要な役割です。
例えば、職場の業務内容に応じた負荷や、同僚との連携が求められる状況を考慮せずに復職を進めると、従業員が再び適応障害やうつ病を発症し、再休職に追い込まれるリスクが高まります。
たとえばこんなケースが…
ある従業員が主治医から「復職可能」の診断を受けましたが、実際の職場環境では集中力や注意力が要求される業務が中心。産業医が職場の状況を確認せず復職を認めた結果、業務についていけず再び休職。チームの負担も増え、職場の雰囲気が悪化してしまいました。
産業医には、職場環境や仕事内容を把握し、主治医の診断を踏まえて企業と従業員に最善の提案を行う能力が求められます。
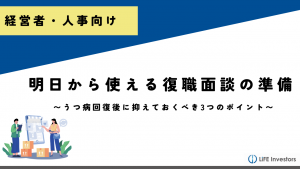
3.虚偽の主張を行う
従業員がこれ以上休むと生活が厳しいはずですから、復職させてあげてください」と感情的に主張する産業医もいます。一見すると従業員の味方のように見えますが、医学的根拠が伴わない判断は、むしろ従業員の健康を害する結果につながりかねません。
短期的には企業が産業医の意見を受け入れることでその場を収めることができるかもしれません。しかし、長期的に見ると、従業員の病状悪化や職場での孤立、さらには同僚への影響など、数多くの問題を引き起こす可能性があります。
たとえばこんなケースが…
復職期限が迫った従業員に対し、産業医が「もう復職可能です」と安易に結論を出しました。しかし、実際には職場でのストレスが重なり、わずか数週間で再休職。従業員本人も精神的に追い詰められ、退職を余儀なくされました。
産業医は、中立的な立場から、企業と従業員の双方にとって最適な判断をする必要があります。感情論に流されるのではなく、従業員の健康状態や業務内容を冷静に評価し、根拠に基づいた判断を下すことが重要です。
つまり、産業医は、中立的な立場で従業員の復職判断を行う必要があるということです。
産業医が企業にもたらす信頼の重要性
産業医は、従業員と企業の双方にとって信頼できる存在であることが最も重要です。「会社側に情報を共有しない」「主治医の意見をそのまま鵜呑みにする」「感情的に判断する」などの特徴が見られる産業医は、結果的に企業と従業員の双方にリスクをもたらします。
そのため、産業医を選ぶ際には、以下の点をチェックしましょう:
- 職場環境を適切に把握する能力があるか
- 中立的な立場を保ち、冷静な判断ができるか
- 企業と従業員の信頼を得るためのコミュニケーションが取れるか
産業医は単なる「コスト」ではなく、企業と従業員の未来を支える「投資」です。信頼できる産業医を選任することが、健康的で生産性の高い職場環境を実現する第一歩となります。
次に、従業員目線で見た「信用できない産業医」の特徴を詳しく解説します。
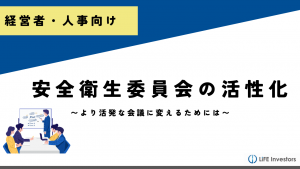
会社とグル?従業員目線の信用できない産業医の6つの特徴
- 1.専門性や倫理観が欠如している
- 2.長時間労働を見て見ぬふりをする
- 3.不正解雇に加担する
- 4.退職を強要する
- 5.従業員の状況や話を全く聞かない
- 6.企業の違法行為を放置する
1.専門性や倫理観が欠如している
「自分の専門ではないので対応できません」と一方的に突き放された経験はありませんか?
産業医の資格は、医師免許があれば約50時間の講習で取得できます。そのため、専門知識や倫理観が十分でないまま対応にあたる産業医が存在しているのも事実です。
しかし、職場で起きる問題は多岐にわたり、個別のケースに柔軟に対応できるプロフェッショナリズムが求められます。適切な知識と倫理観を持った産業医は、企業や従業員双方の立場を理解し、解決策を模索できる存在です。
例えばこんなことが…
産業医がある従業員のメンタルヘルスの問題に対応せず、「それは私の専門ではありません」と言わてしまいました。その結果、従業員は誰にも相談できず問題が悪化。職場全体のモラルが低下してしまいました。
実際に、会社の風土によって起こりうる問題は様々です。それぞれの問題に対応することが重要になってきます。
つまりプロフェッショナリズムを持つ産業医は、適切な知識と倫理観を持ち、第三者として、企業と従業員の双方にとっての行動を模索することができるのです。
「メンタル対応に強い産業医のメリットとは?」
▶︎▶︎▶︎ライフインベスターで詳細を確認してみる
2.職場環境の悪化を放置する
職場環境の改善は医者である自分がやる仕事ではないです」と明言し、明らかにSOSを発している従業員に対して無関心な態度を取る産業医が存在するかもしれません。
企業によっては、急速な成長に伴い入れ替わりの激しい職場環境が形成されることもあります。これは企業の発展過程で避けられない現象かもしれません。しかし、問題はその背景にある場合が多いです。例えば、明らかに上司からの不合理な「パワハラ」が原因で、その上司の直属の部下のみが「うつ病」や「適応障害」を発症しているケースでは、産業医は職場の配置転換や他の具体的な改善策を提案する責任があります。
さらに、単に解決策を提案するだけでなく、企業の成長段階や特性に応じて実行までの具体的な道筋をサポートする姿勢が求められます。産業医がこのような積極的な関与を怠ると、従業員の健康被害が拡大し、企業全体の健全性が損なわれる危険性があります
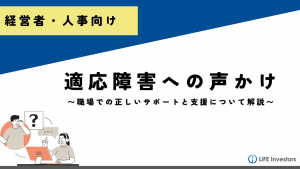
3.不正解雇に加担する
「会社が決めたことだから」と企業側と従業員側からの情報を集める努力をせずに情報を遮断してしまう産業医が稀にいらっしゃいます。
一般的に会社にとって最も大事なことは、売上利益の向上と経営基盤の安定化をすることになります。
つまり、会社が生き残っていくためには、ある程度、コストダウンが必要な場合もあります。特に中小企業(スタートアップやベンチャーを含む)では従業員が少ないためにこれがより強く意識されている側面もあると思います。
しかし、日本の労働契約法や労働基準法などの法律では、労働者の解雇を行うためにしっかりとした手続きを踏むことが明記されています。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法 第16条
つまり、解雇を行う場合は、誠意をもって企業が手続きを行なったかどうかに焦点が当たります。
この手続きを踏んでいく過程で、精神疾患(例:うつ病、適応障害、自律神経失調症など)や身体疾患(例:脳卒中、心筋梗塞、潰瘍性大腸炎など)が関わった場合に企業に所属する産業医との連携が大事になってきます。
逆に、産業医が企業に対してこの行動指針を提案できない場合は、裁判などのトラブルに発展し敗訴する可能性もあります。大事なことは、企業と連携を行い、誠実に物事に対応していくこととなるのです。
4.退職を強要する
企業では、強い退職勧奨の強要が行われていることがあります。そして、このことに加担してしまう産業医がいることも事実です。
この行動には、従業員のことを思っての言動である場合もありますが、「病気もあるし、やめた方がいいよ」と伝えたり、主治医に現状の情報共有もせずに「無理だよ、職場がもうあなたが帰るところはないといってるよ」と言って深い事情を理解しないままに退職を促してしまう産業医は一定数いらっしゃいます。当然、退職の強要は違法になる可能性があります。
大前提として、産業医は中立的な立場で企業毎のフェーズにあった提案をできることが必須になるのです。
5.従業員の状況や話を全く聞かない
「医学や法律でこう決まっていることだからこう対応すべきだよ」と産業医に言われたり、しっかりと論理立てて話した内容が産業医に全く伝わっておらず徒労感を感じたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
対象従業員の現状や相談内容の詳細を確認もせず、医学や法律でこう決まっているからと、一辺倒の判断をしてしまう産業医がいることは事実です。
確かに従業員から見た視点と会社から見た視点では、ギャップが存在することが多々あります。
特に、スタートアップやベンチャーなどの成長途中の企業は、新規投資に資金を投入しているため、社内に余剰資金がほとんどなく、従業員の働く環境や勤務形態などの福利厚生に十分な予算を割けない状況にあることも間々あります。
しかし、事案によっては十分な予算をかけずに手軽に対応ができることもあります。
つまり、産業医は企業と従業員の双方から話を聞き、問題が起きている現場の状況を正確に把握することが大切です。
そして必要であれば、現場の状況を直接見に行く姿勢が重要です。
このような態度がない何事も面倒くさがる産業医は、信用できない産業医と呼ばれても仕方ありません。
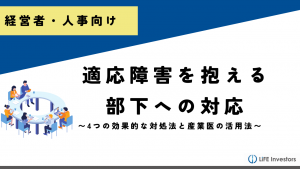
6.企業の違法行為を放置する
意図的に違法行為を行っている企業は少なく、多くの企業では違法行為自体に気づかずしてしまっているということが実情ではないかと思います。
しかし、違法行為に気づかない場合も、事故が起きた際には大きな問題になることが多く、それが回り回って従業員に不利益を生じさせることもあります。これを未然に防止する為に、第三者である産業医が担う役割は大きいです。例えば、月1回の職場巡視を通して施設管理を指摘したり、産業医面談の過程で人事労務管理上の法律上の不備に気づくなどです。
実際に、この違法行為に気づいた場合は、産業保健分野で大事とされる3つの管理
- 作業環境管理:従業員の働く環境の管理
- 作業管理:従業員の作業手順や方法の管理
- 健康管理:従業員の健康の管理
を踏まえて、企業と従業員にとってどのような改善をする事が一番良いかを考えて、適切なタイミングで提言していくことが必要になります。
そして最も避けるべきなのは、
・会社目線:大きな労務リスクを抱えること
・従業員目線:重度な健康障害を引き起こすリスクを負うこと
の2点になります。
会社目線でこの労務リスクが表面化すると、法律で罰せられる可能性が生じるだけでなく、企業のブランドイメージの低下や、在籍する従業員のモチベーションの低下などにも影響が起こり得ます。
このことを避けるために、産業医は企業と従業員の視点を持ちながら、中立的な立場で何が今、一番大切なのかを考え、長期目線でサポートしていくことが大切になるのです。
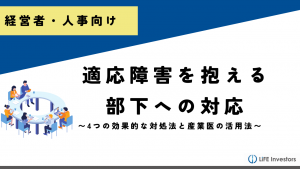
最後に
今回の会社側と従業員側の視点から見た信用できない産業医についてどう感じたでしょうか?もしかしたら会社が契約する産業医の特徴に当てはまった方もいるかもしれません。
実際に信用できない産業医の存在は企業や従業員にとって多くのリスクをもたらします。
信用できない産業医と契約する長期的なリスク
【会社側】
・法律違反の助長
・ブランドイメージの低下
・企業内ガバナンスの低下
【従業員側】
・働く場所や居場所の喪失
・長期的な病気の悪化
上記に挙げた長期的なリスクはただの一例に過ぎません。
そしてここにあげた以外にも、経営や人材の採用に影響が及ぶ可能性があります。
このような事態を避ける為にも、産業医を選ぶ際には信用できない産業医を選択しないようにする必要があります。
そして、最も大事な事は、産業医の存在は企業にとって単なる法律上のコストではなく、より良い成長のための投資という視点です。
最後に、信用できる産業医にとっての必要条件を以下にチェクリスト形式でまとめました。
あなたの会社の産業医は大丈夫??産業医チェックリスト
□ 知識や経験の有無 :復職対応やメンタル対応をしたことがあるか
□ 説明のわかりやすさ:専門用語ではなく従業員にわかりやすい用語を使えるか
□ 傾聴力:経験や知識だけを主張せず、会社の状況を踏まえながら一緒に考えてくれるか
□ 態度:横柄な態度ではなく、話しやすい態度を取ることができるか
□ 迅速な連絡対応:メールや電話は当日中か翌日には返事があるか
上記のチェックリストは信用できる最低限の産業医の条件をまとめています。つまりこのチェックリストから漏れる産業医がいる場合は産業医を変更することも検討しても良いかもしれません。
ライフインベスターズでは、コミュニケーション能力や専門性など、一定の基準を満たした産業医が所属しております。産業医の交代を含め何かお困りやご不満がございましたら、無料のオンライン相談も受けつけておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。