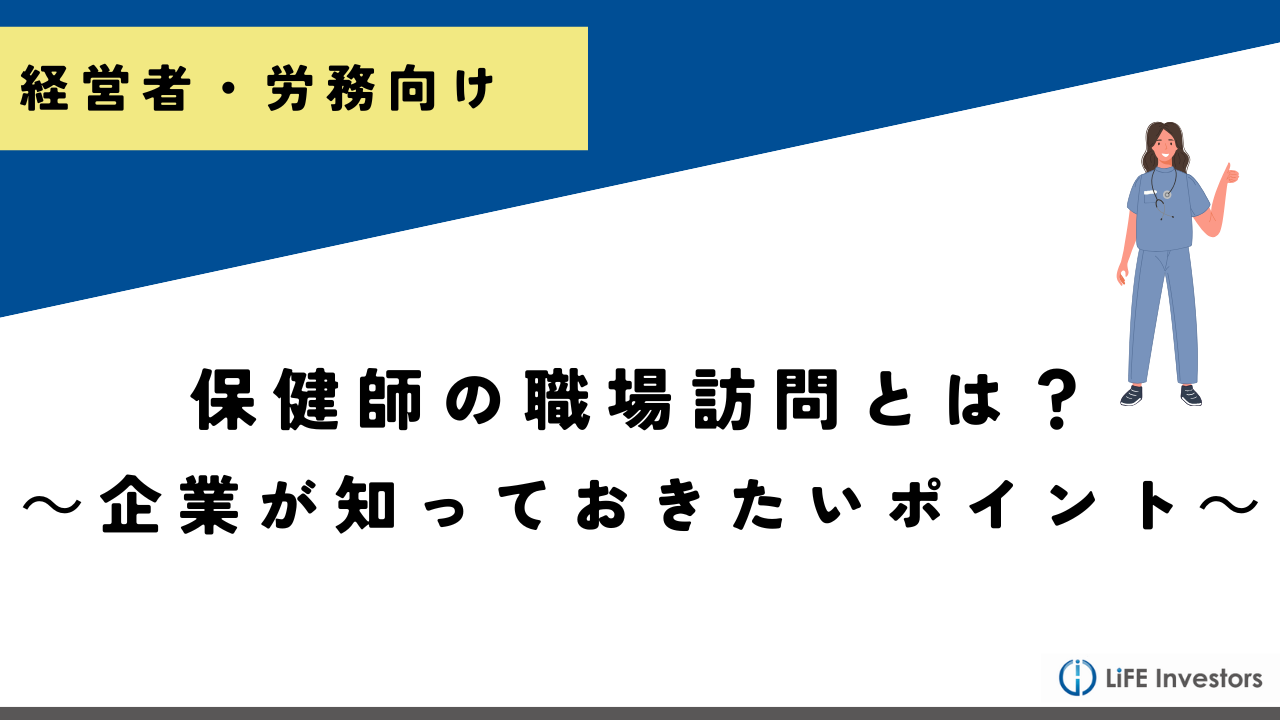この記事はこのようなお悩みをお持ちの方に向けて書いています。
・保健師の職場訪問について知りたい
・産業医との違いや、両者の連携方法を理解したい
・健康経営を進めたいが、何から始めればいいか分からない
「うちの会社でも保健師が訪問に来てくれるようになった」
最近、そんな声を耳にする企業担当者が増えています。
従業員の健康を守る取り組みは、法令遵守のためだけでなく、企業の持続的成長を支える戦略的投資として位置づけられるようになりました。
その中で注目されているのが、保健師による職場訪問です。
しかし、「保健師の訪問は何をしてくれるの?」「産業医とどう違うの?」「法的義務はあるの?」など、実際のところを詳しく理解している企業はまだ多くありません。
この記事では、保健師の訪問活動の目的や具体的な内容、法的な位置づけ、導入のメリットなどを包括的に解説します。
保健師が企業を訪問する目的とは
保健師による職場訪問の目的は、単に「健康相談」や「面談」を行うことではありません。
本質的には、従業員の健康リスクを早期に把握し、働きやすい職場づくりを支援することにあります。
主な目的は以下の3つです。
1.従業員の健康状態の把握と個別支援
健康診断やストレスチェックの結果をもとに、心身のリスクを可視化します。
必要に応じて個別面談を行い、生活習慣の見直しや医療機関受診をサポートします。
2.職場環境のリスク評価と改善提案
現場を実際に観察し、照明・換気・休憩環境・作業姿勢などの要因を確認します。
また、産業医と連携しながら、環境改善の提案や再発防止策を企業へ助言します。
3.健康意識の向上と教育活動
従業員の健康意識を高めるために、健康講話やセルフケア研修を実施します。
保健師は医療知識を持ちながらも「生活者目線」でアドバイスできる存在です。
これらの活動は、「病気を治す」よりも「健康を維持する」ことに重点が置かれています。
つまり、保健師の訪問は「一次予防=未然防止」の取り組みといえます。
保健師の訪問内容:現場での具体的な活動とは

保健師が企業を訪問する頻度は、月1回〜四半期に1回など、企業の規模や課題に応じて異なります。
1回の訪問で行われる業務は多岐にわたり、職場全体と個人の両面をカバーします。
【訪問時に行われる主な活動例】
- 健康診断後の有所見者フォローアップ面談
- 長時間労働者・高ストレス者へのヒアリングと生活支援
- ストレスチェック結果の分析・職場単位での傾向報告
- 職場巡視の同行(産業医との連携)
- 衛生委員会への出席と健康情報の提供
- 健康啓発イベントやワークショップの実施
保健師が重視しているのは「関係構築」
訪問時には、従業員との何気ない会話を通して「職場の空気感」や「小さな異変」を察知することも重要な仕事です。
例えば、「最近、元気がない社員が多い」「特定部署だけ残業が増えている」といった現場の声を、早期にキャッチして経営層や産業医へ伝えます。
つまり保健師は、企業における“健康のセンサー”としての役割を果たしています。
保健師との連携に法的義務はあるの?
ここで多くの企業担当者が気になるのが、「保健師と契約・連携することは義務なのか?」という点です。
結論からいうと、保健師との連携は法的義務ではありません。
労働安全衛生法第13条では、「常時50人以上の労働者を使用する事業場には産業医の選任が義務」とされています。
しかし、保健師の配置については法的な義務規定は存在しません。
そのため、企業が保健師を配置していなくても、行政指導や罰則を受けることはありません。
ただし、行政は保健師の活用を強く推奨しています。
厚生労働省が発行する『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』では、産業保健スタッフとして保健師が明記されています。
つまり、法的義務ではないが、行政的には「努力義務」に近い推奨レベルにあるのです。
実態:健康経営企業の多くが保健師を導入
実際のところ、健康経営優良法人(ホワイト500など)に認定されている企業の多くが、「産業医+保健師」の連携体制を構築しています。
保健師が現場を継続的に支援することで、
- メンタル不調者の早期発見
- 職場環境の改善提案
- 産業医面談のフォローアップ
といった効果が得られやすくなるためです。
つまり、法的には任意でも、実務上は“導入しないリスク”が高まる時代に入っています。
産業医との違いと連携のポイント
保健師と産業医はともに「企業の健康を支える専門職」ですが、その役割には明確な違いがあります。
| 産業医 | 保健師 | |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 労働安全衛生法で選任義務あり | 法的義務なし (行政が活用を推奨) |
| 主な役割 | 医学的判断・指導、就業判定、制度整備 | 健康相談・生活支援・現場改善 |
| 活動頻度 | 月1回(法令上) | 月1〜複数回 (企業の任意設定) |
| 得意分野 | 法令対応・リスク管理 | コミュニケーション・教育・サポート |
| 特徴 | 経営・法務寄りのアドバイザー | 現場・従業員寄りの伴走者 |
産業医が制度的・法的観点から助言する一方、保健師は現場で従業員に寄り添いながら実践的支援を行います。
この連携により、「制度と現場のギャップ」が埋まり、健康管理体制がより機能的になります。
保健師訪問が企業にもたらすメリット
保健師の訪問を導入している企業では、以下のような成果が報告されています。
- メンタル不調の早期発見・再発防止
従業員が相談しやすい窓口を設けることで、重症化を防ぐことができます。
- 離職率の低下とエンゲージメントの向上
健康支援を受けた従業員は「会社に大切にされている」と感じ、定着率が上がります。
- 産業医との連携効率の向上
保健師が事前に情報を整理・共有することで、産業医面談がより効果的になります。
- 健康経営の評価向上
従業員の健康支援体制が整っていることが、健康経営優良法人などの認定取得にもつながります。
こうした効果は、単なる“福利厚生”にとどまらず、経営リスクの低減や組織パフォーマンスの向上という形で企業に還元されます。
保健師の訪問を効果的に活用するためのポイント
導入時に意識したいのは、以下の3つの視点です。
1.目的を明確にする
「どの課題を解決したいか」を明文化することで、保健師の活動内容を最適化できます。
(例:「メンタル不調者対応」「健診フォロー強化」「休職者支援」など)
2.社内体制を整備する
人事・衛生委員会・経営層が一体となってサポートする仕組みを作ることが大切です。
3.従業員に開かれた環境を作る
相談窓口を周知し、プライバシーに配慮した面談環境を整えることで、従業員が安心して相談できます。
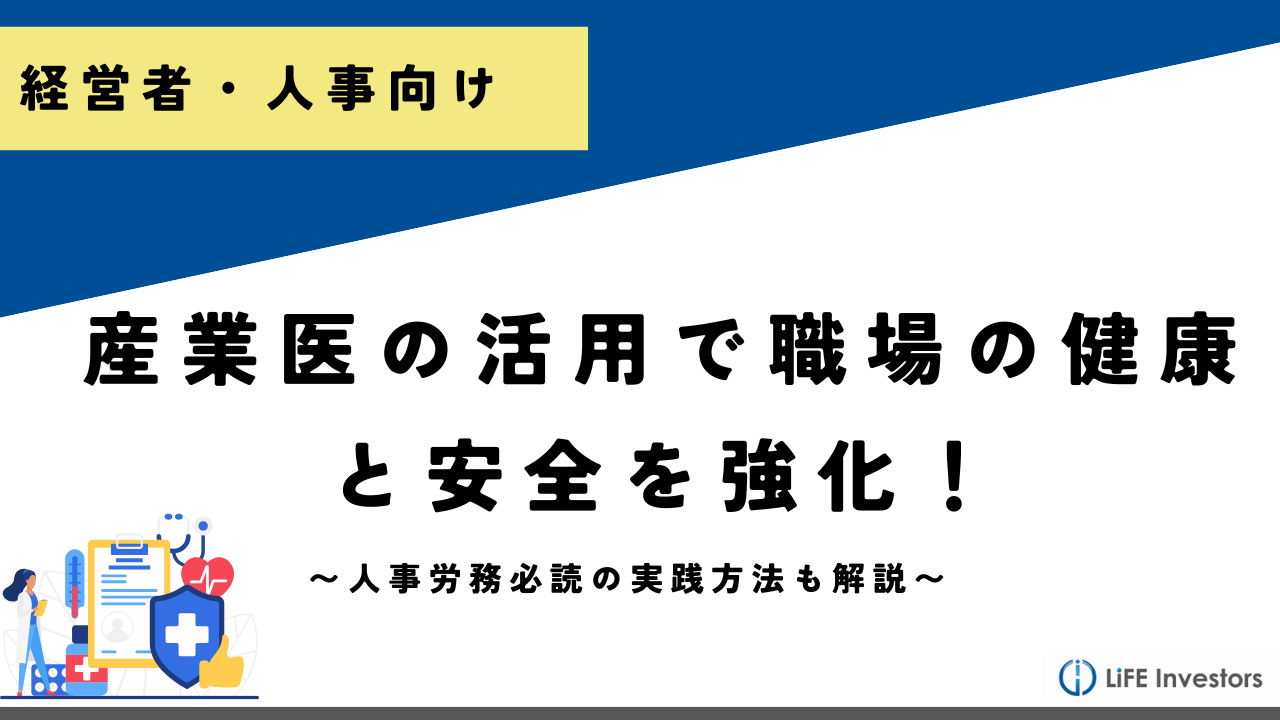
まとめ
保健師の訪問は、法的義務でこそありませんが、現代の健康経営には欠かせない取り組みです。
産業医の医学的サポートに加え、保健師の現場支援が加わることで、企業は「制度と現場の両輪」で従業員の健康を守ることができます。
選任の法的義務がある産業医の方が目立ちがちですが、「産業医にすべてを任せるとコストがかかる」とはいえ、「人事部だけで対応しようとすると専門知識が足りず不安」と感じる企業も少なくありません。
そこで最近では、月に固定の時間で訪問またはオンライン対応を行い、保健師に健康管理業務を外注するケースが増えています。
企業の健康管理は“義務”から“戦略”へ。
これからの時代、保健師との連携は「選択肢」ではなく「投資」といえるでしょう。
保健師訪問や健康経営の体制づくりを支援する「ライフインベスターズ」
健康経営の導入を検討している法人様や、保健師・産業医の連携体制を整えたい方には、ライフインベスターズのサポートがおすすめです。
ライフインベスターズでは、
- 産業医・保健師の紹介
- 職場巡視・面談体制の構築支援
- 健康管理システムやストレスチェックの運用支援
など、法人様の課題に合わせて柔軟に対応しています。
対面訪問だけでなくオンライン対応も可能で、全国の企業に対応できる体制を整えています。さらに、複数の保健師と提携しており、法人様のご要望に応じた最適な人材をご紹介することができます。
また、初めての導入でも安心できるよう、無料相談・資料請求を受付中です。
専門家が丁寧に現状をヒアリングし、最適な健康支援体制の構築をご提案します。
企業の健康づくりを、今こそ次のステージへ。
保健師とともに「働く人が健やかに輝く職場づくり」を始めましょう。
【参考文献】