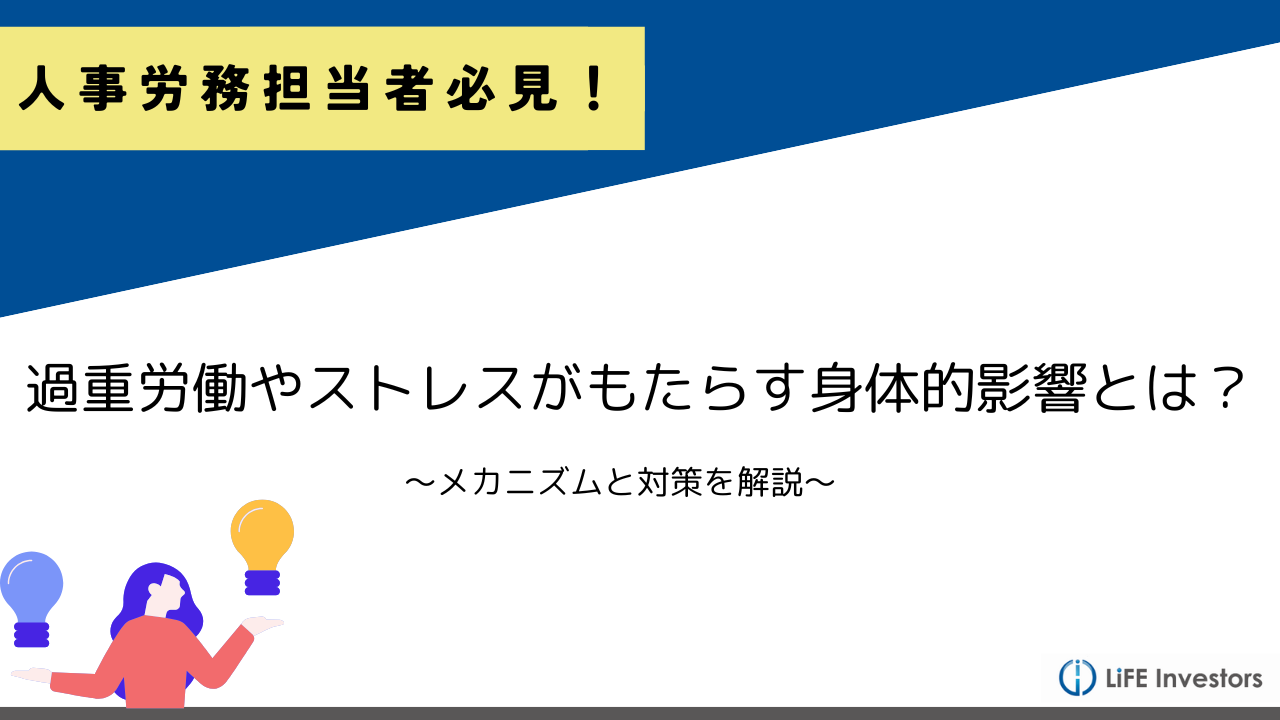この記事はこのような方に向けて書いています。
・過重労働がメンタルにどのような影響を及ぼすのか知りたい方
・過重労働問題の解決に取り組みたい方
近年、日本では過重労働が深刻な社会問題となっています。長時間労働や過度な業務負担によって、心身の健康を損なうケースが増えており、働き方改革が進められる中でも、その影響は依然として多くの職場で見られます。
特に、過重労働によって引き起こされるストレスは、単なる疲労感にとどまらず、メンタルヘルスに深刻な影響を及ぼすことが知られています。
本記事では、過重労働がどのようにストレスを引き起こし、それがメンタル不調に至るのかを解説しています。ぜひ本記事を過重労働問題をどう解決すればいいのか考えるきっかけにしてみてください。
過重労働とは?
過重労働とは、労働者に過度な負担がかかる働き方のことです。単に「残業が多い」というだけでなく、業務量の多さや責任の重さ、プレッシャーの強さなども関係します。過重労働には以下のようなものが挙げられます。
①長時間労働
法定労働時間は1日8時間、週40時間と設定されています。残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできないと法律で定められています。これらを大幅に超過していると長時間労働と考えられます。
健康リスクに関する残業時間の目安は以下の通りです。
- 残業月45時間以上 → 健康リスク増加
- 残業月80時間以上 → 労災認定基準に該当
- 残業月100時間以上 → 健康に極めて高いリスク
②不規則な勤務形態
- 夜勤・交替制勤務
- 休日出勤・連続勤務
- 長時間の出張・移動
これらは体内リズムを崩し、疲労回復を妨げる原因になります。
③精神的負荷の大きい業務
- 高い責任を伴う仕事
- クレーム対応や対人ストレスの多い業務
- 過酷な作業環境(高温・低温・騒音・粉じん など)
仕事の「量」だけでなく、「質」もメンタルに影響を与えることを理解しておく必要があります。
過重労働が体に与える影響とそのメカニズム
過重労働は、心身の健康に重大な影響を与えることが広く知られています。その影響は、睡眠不足、ストレスホルモンの増加、免疫機能の低下など、さまざまな形で現れます。ここでは、過重労働がどのように身体へ影響を与えるのか、そのメカニズムを詳しく解説します。
過重労働が健康に影響するポイント
①睡眠時間の減少
労働時間が長くなるほど、自由に使える時間が減少し、睡眠時間が短縮されます。
睡眠時間が短くなると、睡眠不足により脳の回復が不十分となり、ストレス耐性が低下するほか、慢性的な疲労が蓄積します。
睡眠時間が短いほどメンタルヘルス不調のリスクが高まります。特に、6時間未満の睡眠が続くと抑うつ症状が顕著に増加することが研究で示されています。
時間外労働が50時間を超えると睡眠時間が6時間未満になる傾向があり、100時間を超えるとさらに悪化します。
② ストレスによる生体反応
過重労働が続くと、コルチゾールやアドレナリンなどのストレスホルモンが過剰に分泌され、交感神経が過剰に活性化します。これにより、血糖値や血圧の上昇を引き起こします。 血糖値の上昇は糖尿病のリスク増加、血圧の上昇は高血圧・心筋梗塞のリスク増加につながります。
交感神経の活性化に伴い副交感神経の働きが低下するのでますますリラックスできなくなってしまいます。
また、ストレスが長期間続くと、脳内の神経伝達物質(セロトニン・ドーパミン)のバランスが崩れ、慢性的なメンタルヘルスの不調を引き起こします。
過重労働がもたらす健康リスク
①心血管疾患(脳卒中・心筋梗塞)リスクの増加
先ほど説明した通り、過重労働によるストレスと長時間労働の影響で、血圧や血糖値が上昇し、血管が慢性的にダメージを受けることになります。これを放置すると動脈硬化が進行し、脳血管疾患や虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)の発症リスクが高まってしまいます。 労災認定基準でも、月80時間以上の時間外労働が続くと、脳・心臓疾患のリスクが急激に高まるとされています。
②消化器系の不調
ストレスによって胃酸の分泌が増加し、胃炎や胃潰瘍を引き起こしやすくなります。 また、腸内環境が悪化し、便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群のリスクが増加します。
③メンタルヘルス不調
ストレスが慢性化すると、脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミン)が減少し、抑うつ症状・不安症状・意欲低下が発生し、最悪の場合うつ病やバーンアウト症候群に至ります。
*バーンアウト症候群とは、それまでモチベーションを高く保っていた人が、突然やる気を失ってしまう病気のことです。
特に100時間以上の時間外労働が続くと、メンタルヘルスの悪化が顕著になることが研究で示されています。
メンタル不調を防ぐ職場での対策
これらの問題に対して、企業・個人それぞれが適切な対策を講じることが重要です。ここでは、企業・個人・管理職それぞれの立場での具体的な対策を紹介します。
企業が取り組むべき対策
1.定期的なストレスチェック制度の導入
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスの状態を把握し、早期に対応するための重要な取り組みです。厚生労働省が定めるストレスチェック制度では、50人以上の事業場での実施が義務付けられていますが、企業規模に関わらず導入を検討することが望ましいです。
2.メンタルヘルス研修の実施
メンタルヘルスについての理解を深めるために、定期的な研修を実施することが効果的です。特にストレス対処法やメンタル不調の兆候についての知識を身につけることで、社員一人ひとりが自身の健康を守る力を養えます。特に、管理職向けの研修では、部下のメンタルヘルスケアや適切な声かけの方法を学ぶことで、職場全体のサポート体制を強化できます。
3.相談窓口の設置
従業員が安心して悩みを相談できる環境を整えることも重要です。社内外の相談窓口を設置することで、メンタル不調に陥る前に適切なサポートを受けることができます。相談窓口を活用しやすいように、プライバシーを確保し、気軽に利用できる雰囲気を作ることが大切です。産業医の活用もご検討ください。
個人でできる対策
1.リラックス法
日常的にリラックスする習慣を持つことで、ストレスを軽減できます。深呼吸も副交感神経を活性化させるので有効です。
2.睡眠の質を高める工夫
睡眠不足はメンタル不調の大きな要因となります。睡眠時間を増やすのも大切ですが、質の良い睡眠を確保することも同じくらい重要です。寝る前のスマホ・PC使用、カフェインやアルコールの摂取は控え、寝る前にリラックスする習慣を作りましょう。また、毎日同じ時間に寝る習慣をつけ、体内リズムを整えるのも効果的です。良質な睡眠をとることで、ストレス耐性が向上し、仕事のパフォーマンスも向上します。
管理職の役割と職場のサポート体制
1.部下のストレスサインの見極め
管理職は、部下のメンタルヘルスを守る重要な役割を担っています。ストレスが溜まっているサインを見逃さないことが大切です。表情や態度の変化(無表情、イライラしやすい)、
遅刻・欠勤の増加、業務ミスや集中力の低下などのサインが見られたら、早めに声をかけ、適切なサポートを行いましょう。
2.ワークライフバランスを考えた業務設計
そもそも過重労働状態にならないようにすることが健康に悪影響を及ぼさないために大切です。仕事の負担を適切に管理し、従業員が無理なく働ける環境を整えることは管理職の重要な役割の一つでしょう。業務量の適正な配分、長時間労働の防止、在宅勤務やフレックスタイム制度の活用、休暇の取得の促進などを進めましょう。休憩時間はしっかり取るよう促すのも忘れないようにしましょう。
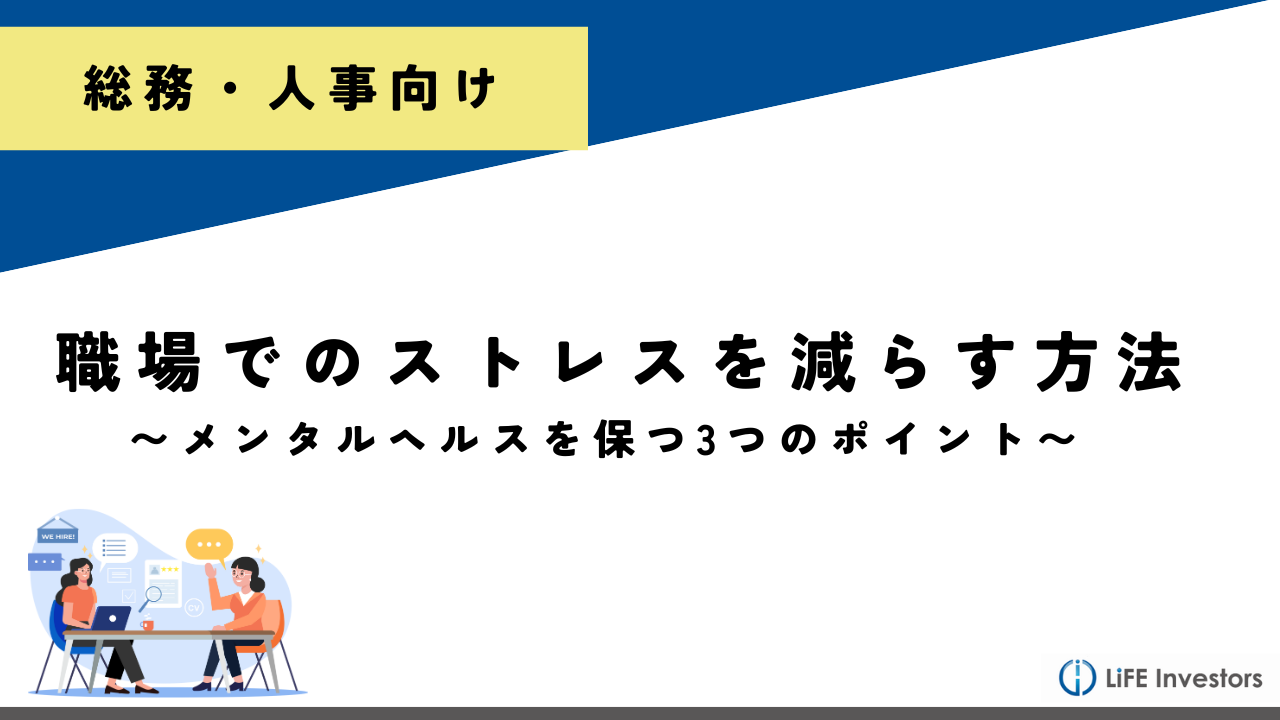
まとめ
過重労働は心身に深刻な影響を与える働き方です。脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調のリスクを大幅に高めることは本記事を通してお分かりいただけたかと思います。
過重労働を防ぐためには、労働時間の適正管理、業務負担の分散、職場のメンタルヘルス対策の強化が不可欠です。個人・企業・社会全体でこれらの問題に取り組むことが大切です。働く環境の改善と適切なセルフケアを通じて、健康を守りながら持続可能な働き方を模索しましょう!
ライフインベスターズでは、コミュニケーション能力や専門性など、書類や面接審査を通じて一定の基準を満たした厳選した産業医が所属しております。
大手法人様はもちろん、これから衛生委員会を立ち上げるスタートアップ・ベンチャー企業様への対応経験も豊富にございます。特にメンタル対応についてお困りの法人様から専門性の高さで高くご評価いただいておりますので、産業医の交代を含め、何かお困りやご不満がございましたら、無料のオンライン相談も受けつけておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
【参考文献】
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo05_1.html