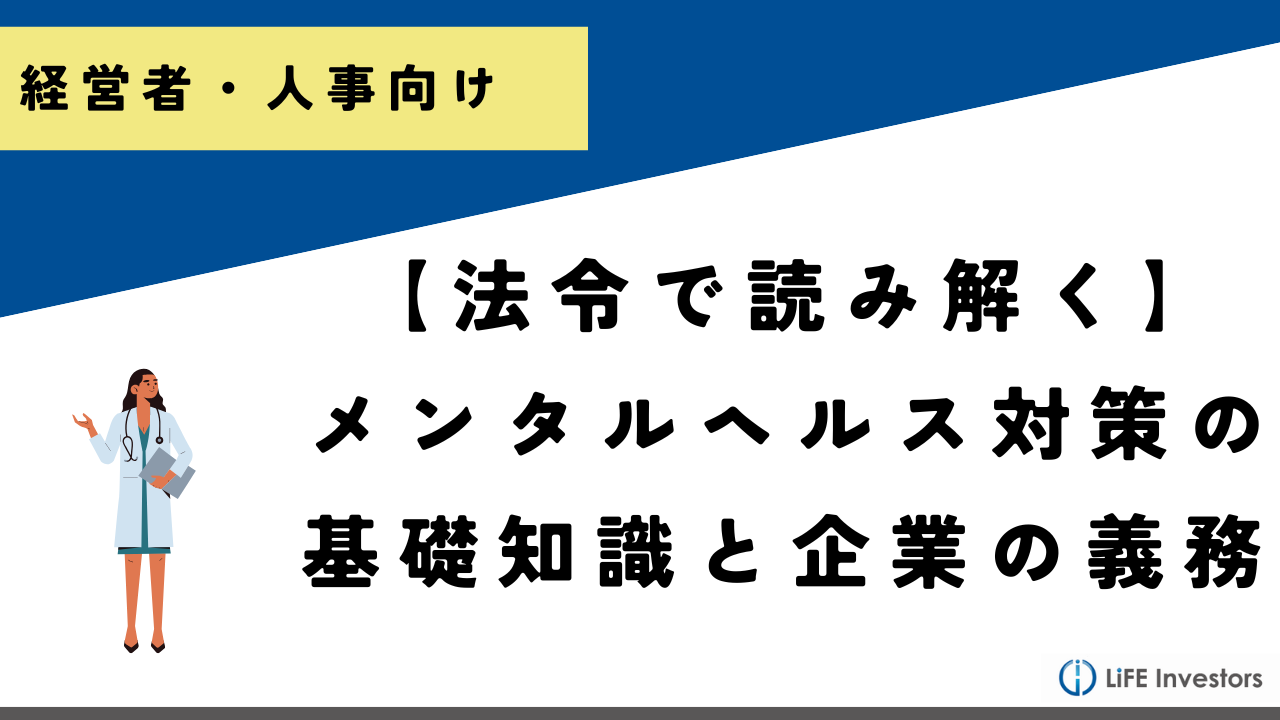この記事はこのような方に向けて書いています。
・メンタルヘルス対策に不安があり、法律に基づいた正しい対応を知りたい人事担当者の方
・労働安全衛生法を含む法令の要点を把握したい方
・「何をすれば法令遵守になるのか」を明確にしたい中小企業の経営者・総務責任者の方
「ストレスチェックはやっているけれど、本当に正しく運用できているのか不安」「メンタルヘルス不調で従業員が休職したが、会社としてどう対応すべきかわからなかった」——そんな経験はありませんか?
メンタルヘルス対策は、人事・労務の感覚的な領域ではなく、法律に基づく企業の義務と明確に位置づけられています。
特に「労働安全衛生法」は、従業員の心の健康を守るための法的枠組みを整えており、対策の出発点となります。
この記事では、企業が押さえるべきメンタルヘルス関連の法律・制度を体系的に解説し、実務と法令をつなげてわかりやすくお伝えします。
労働安全衛生法とメンタルヘルス
メンタルヘルス対策の中心的な根拠は、労働安全衛生法です。
この法律は、職場における労働者の「安全」と「健康」を確保し、快適な職場環境を形成するために制定されたものです。
メンタルヘルスに関連する主要条文
(産業医等)
第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
常時50人以上の従業員を擁する企業は産業医を選任し、月1回以上の職場巡視、健康指導などを行わせる必要があります。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
企業は年1回以上、ストレスチェックを行い、その結果の本人への通知と面接指導体制の整備を行うことが求められています。
(健康教育等)
第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
企業は心身の不調リスクに対して早期に対応することが求められています。
特に上2つの条文は「努力義務」ではなく、「義務」として明記されています。違反した場合、労働基準監督署からの指導や是正勧告、場合によっては行政処分の対象になる可能性もあります。
ストレスチェック制度の法的根拠と実務義務
2015年12月に施行された改正労働安全衛生法により、ストレスチェック制度が導入されました。
法的根拠:第66条の10(先述)
この条文では以下の義務が定められています。
- 常時50人以上の事業場における年1回以上のストレスチェックの実施
- 高ストレス者が希望した場合の医師による面接指導
- 面接後、医師の意見に基づいて必要な就業上の措置を講ずる義務
実務上の注意点
- チェック実施者は医師、保健師、または研修済みの看護師・臨床心理士など
- 結果の通知は本人のみに通知し、同意なく第三者に開示してはならない
- 実施後は集団分析の結果を活用して職場環境の改善につなげることが望ましい
50人未満の事業場では努力義務とされていますが、法令リスク回避や社員定着を考えると、任意実施も十分なメリットがあります。
産業医の選任と役割
法的根拠:第13条(先述)
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医の選任が義務です。
選任された産業医は、事業者に対し健康管理に関する意見を述べる義務を負い、労働者の健康確保を支援します。
産業医の主な役割
- ストレスチェック後の高ストレス者への面接指導
- 職場巡視によるリスク評価と改善提案
- 長時間労働者への健康指導
- 精神疾患による復職支援と就業配慮の判断
産業医の意見は、事業者の就業上の措置や労働時間管理にも大きな影響を与えるため、形式的な契約にとどまらず、実務レベルでの連携が重要です。
安全配慮義務と企業のリスク管理
労働契約法第5条に基づき、使用者には労働契約に付随する「安全配慮義務」が課されています。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
これは、従業員が安全・健康に働けるよう必要な配慮を行う義務です。
メンタルヘルス領域で問題となるケース
- 長時間労働を放置した結果、うつ病を発症
- 職場のハラスメントを看過したことで精神的疾患を発症
- ストレスチェック結果を無視して対応を怠った
これらのケースでは、企業が損害賠償を請求されるリスクがあり、裁判でも安全配慮義務違反が認められることがあります。
実践につなげる法令対応のチェックリスト
中小企業が今すぐ確認すべき法令対応状況をチェックリストにまとめました。
- 常時50人以上の事業場において、産業医を選任している
- ストレスチェックを年1回、正しい手順で実施している
- 高ストレス者に対して、医師による面接指導を行っている
- 面接指導の結果をもとに、必要な就業上の措置を講じている
- 集団分析を活用し、職場環境の改善につなげている
- 労働時間・人間関係などに起因するメンタルリスクを把握している
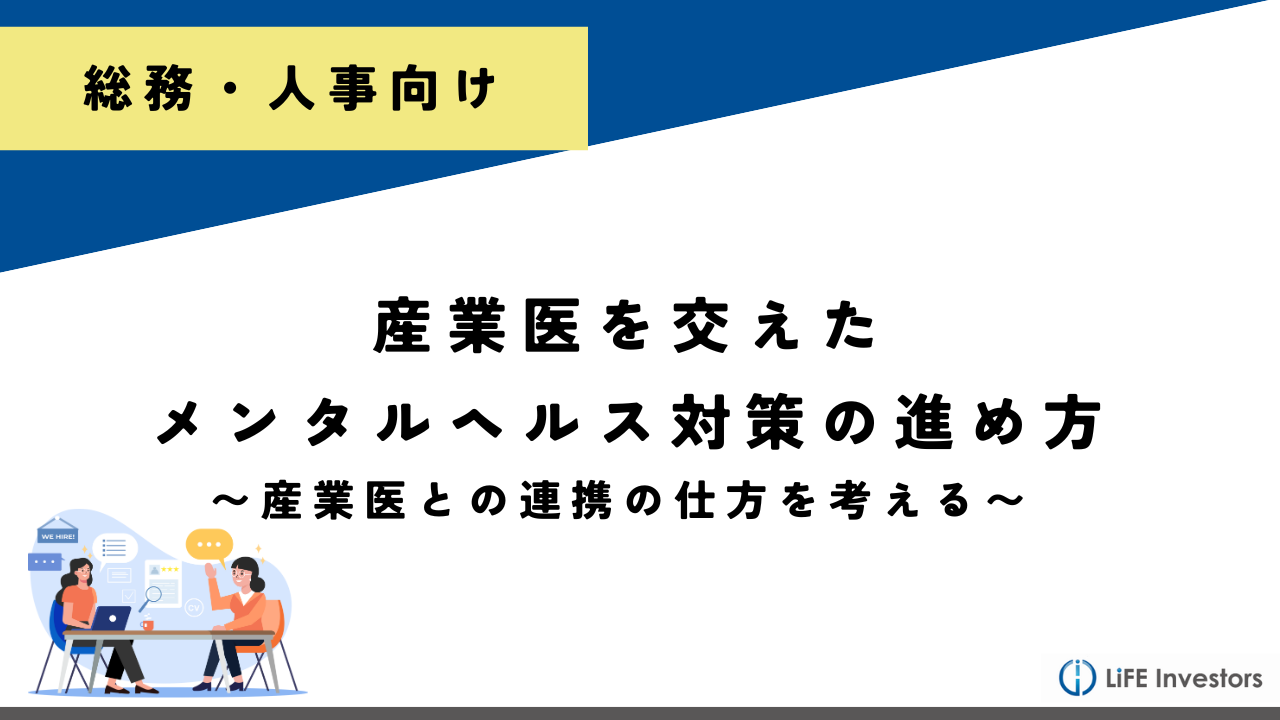
まとめ|法令に強くなることが、メンタルヘルス対策の第一歩
メンタルヘルス対策は、感覚的な「良かれと思って」の対応ではなく、法律に基づいた正確な知識と手順に支えられてこそ機能します。
とくに中小企業にとっては、法令違反による信用失墜や訴訟リスクを回避する意味でも、基礎知識の習得と制度の整備は急務です。まずは法的な枠組みを理解し、必要なステップを一つずつ実践していくことから始めましょう。
メンタルヘルス対策を「法令順守」と「実践支援」の両面でサポートします
「産業医の選任方法がわからない」「ストレスチェックの導入が不安」
そんなお悩みを持つ中小企業に向けて、ライフインベスターズでは、法令に沿った形でのメンタルヘルス支援を専門的に行っています。
- 経験豊富な産業医の派遣
- ストレスチェック制度の設計・実施サポート
- 復職支援・面談対応・衛生委員会への参加など
✅ 全国対応、法令・実務に精通した専門家がサポートします
✅ 中小企業に特化した柔軟な対応が可能です
【参考文献】