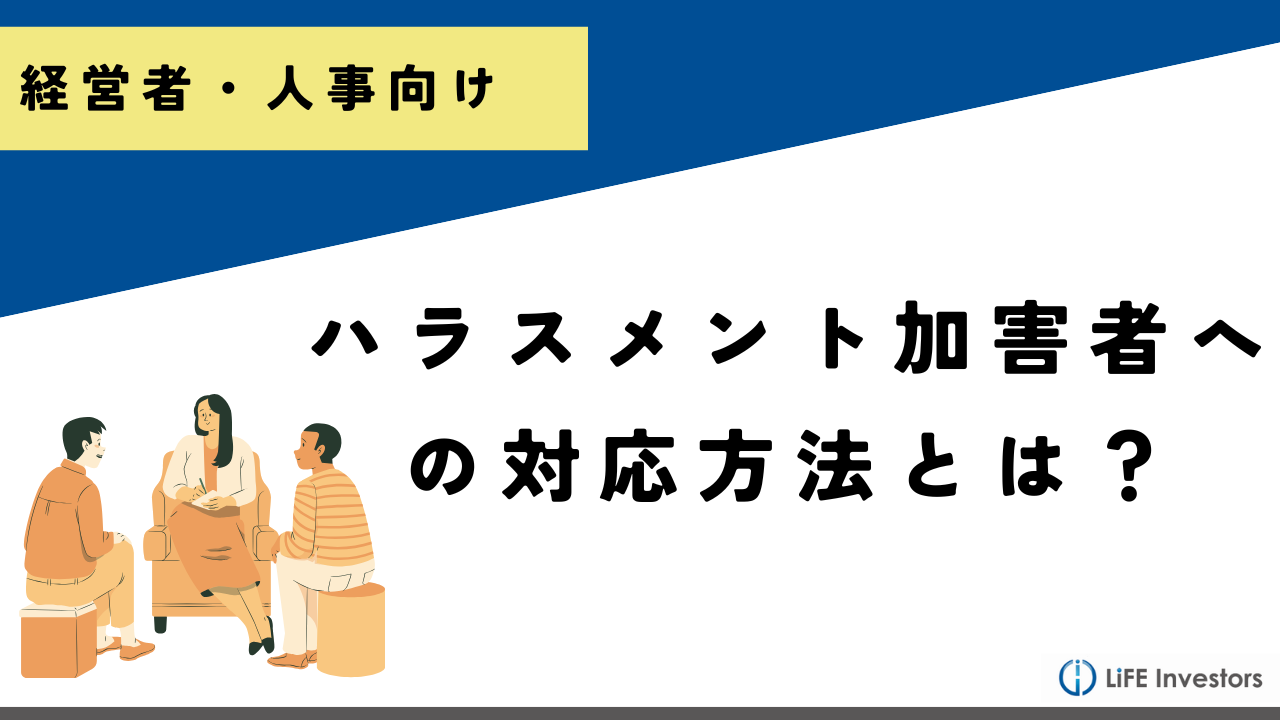この記事はこのようなお悩みをお持ちの方に向けて書いています。
・社内でハラスメントの相談・通報があり、どう対応すべきか悩んでいる
・ハラスメント加害者への対処方法を体系的に理解したい
・職場トラブルを未然に防ぎ、健全な職場環境を維持したい
「職場でハラスメントの相談があったけど、加害者にどう対応すればいいのかわからない…」
このような声を人事の方からよく聞きます。被害者保護に目が向きがちですが、加害者への対応も同様に重要です。対応を誤ると、再発リスクや組織の信頼低下につながるおそれがあります。
本記事では、ハラスメント加害者への適切な対応方法をステップごとにわかりやすく解説します。問題解決の道筋を明確にし、職場の信頼回復につなげましょう。
ハラスメントの加害者とは?その範囲と背景にある意識のズレ
ハラスメントの「加害者」と聞くと、一部の攻撃的な社員や、いわゆる「問題行動を繰り返す人物」を思い浮かべる方も少なくないかもしれません。しかし実際には、職位や役職、年齢や性別に関係なく、誰もが加害者になりうるというのが現実です。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
- 上司が部下に対して過度な叱責を繰り返す(パワハラ)
- 同僚同士で不用意な性的な話題を共有する(セクハラ)
- 社員が取引先や顧客から過剰な要求を受けている(カスタマーハラスメント)
- 部下が上司に対して過度な反抗や陰湿な嫌がらせを行う(逆パワハラ)
つまり、「上から下」「下から上」「横の関係」「社外からの影響」など、ハラスメントはさまざまな方向で発生しうるものであり、それに関与する人物も多様です。
加害者に共通する“認識のズレ”
ハラスメント加害者の多くは、自らが加害行為をしているという自覚がないケースがほとんどです。次のような認識のズレが、その背景にあることが多く見受けられます。
- 自分の言動を「指導」「教育」「軽い冗談」と誤解している
例:「このくらいの叱責は当たり前」「昔はもっと厳しかった」
- 被害者の受け取り方に無関心・軽視している
例:「あの人は神経質すぎる」「これくらいでハラスメントなんて大げさ」
- 組織の文化や風土に無自覚である
例:「うちの部署では普通のこと」「みんなもやっている」
このような思考に陥っている場合、たとえ本人に悪意がなかったとしても、結果として相手に苦痛や不利益を与えていればハラスメントに該当する可能性があります。
ハラスメントの「加害者」を正しく捉える重要性
加害者=悪人、という単純な図式で捉えてしまうと、問題の本質が見えにくくなります。多くのケースでは、無意識の偏見や時代錯誤な価値観が原因となっており、本人も気づかぬまま行動してしまっているのが実情です。
だからこそ企業としては、加害者の言動を一方的に断罪するのではなく、背景や意図を丁寧に把握し、必要に応じて専門家の支援も得ながら、再発防止と改善につながる対応をとることが求められます。
ハラスメントは個人の問題であると同時に、組織の姿勢や文化が映し出される「職場全体の問題」でもあります。加害者をどう捉え、どう支援・指導していくかが、企業の真価を問われる場面と言えるでしょう。
ハラスメント加害者への初期対応

通報や相談があった場合、最初に重要なのは被害者と加害者を隔離し、冷静な状況を作ることです。同時に、加害者に対しては以下のような初動対応が求められます。
- 一方的に断罪せず、事実確認の前提として事情を丁寧に聞く
- 感情的にならず、中立的な立場を保つ
- 行為を否定された場合も、調査を行う旨を伝える
この段階では、「ハラスメントの疑いがある」という事実に基づき、調査の必要性を説明するにとどめましょう。
調査と事実確認のポイント
ハラスメント対応において、調査と事実確認は最も重要なプロセスの一つです。
ここを曖昧にしたまま処分や判断を下すと、被害者・加害者の双方にとって不公平な対応となり、組織としての信頼性を大きく損ねる結果にもつながりかねません。
特に、ハラスメントは「言った・言わない」「受け取り方の違い」など主観的な要素が絡みやすいため、客観性と中立性を確保する姿勢が何よりも大切です。
調査の進め方とポイント
調査を実施する際は、以下の基本ポイントを意識しましょう。
✔ 複数の関係者から個別にヒアリングを行う
被害者本人だけでなく、加害者、当該現場に居合わせた第三者(目撃者)などからも中立的かつ個別に話を聞きます。集団での聴取は、発言が抑制される恐れがあるため避けるべきです。
✔ 発言・行動の日時、場所、具体的な内容を記録する
「いつ」「どこで」「誰が」「何を言った/したか」を、できる限り詳細かつ正確に書面に残すことが重要です。証拠があれば(メール、録音、チャットログなど)、その提示も求めます。
✔ 加害者・被害者いずれかに偏った見方をしない
たとえ加害者が上司や経営層であっても、立場による“忖度”をせず、中立の立場で事実に向き合うことが求められます。逆に、被害者側の主張に全てを委ねるのも危険です。
✔ 調査結果は文書でまとめ、関係部署で共有・保管する
最終的な判断や処分の根拠となるため、調査の過程・内容・結論は文書化し記録として残すことが不可欠です。個人情報保護の観点からも、適切な管理体制を整えましょう。
調査の客観性を担保するために
社内だけで調査を完結しようとすると、「公平性が担保されていない」「身内びいきではないか」といった疑念が生じやすくなります。こうした場合には、外部の専門家の力を借りることも有効です。
- 産業医:メンタルヘルスへの影響や職場環境全体の評価
- 弁護士:労働法・労働契約法に基づいた法的な観点からのアドバイス
- 社労士や第三者機関:調査実務や処分決定の適正性判断
外部支援を活用することで、透明性・客観性・正当性が保たれ、調査結果に対する納得度も高まります。
加害者への処分・指導の方法
ハラスメントの事実が客観的に確認された場合、企業は加害者に対して適切かつ合理的な処分・指導措置を講じなければなりません。対応を怠ったり、曖昧なまま放置したりすると、被害者の不信感を招くだけでなく、企業全体が「問題を容認している」と受け取られかねません。
一方で、処分が過度であった場合には、加害者本人からの法的な反訴(不当解雇・名誉毀損など)につながるリスクもあります。そのため、企業は「再発防止」「組織の信頼回復」「労使双方の納得感」を視野に入れ、バランスの取れた対応が求められます。
処分の種類と適用の考え方
加害行為の悪質性・継続性・影響範囲などを総合的に判断し、社内規定(就業規則など)に則った処分を行うことが原則です。よくある対応例は以下のとおりです。
- 厳重注意・始末書の提出
軽微な行為や、本人に反省の態度が見られる場合などに適用します。本人に非を自覚させ、文書として記録に残します。
- 配置転換・異動
当事者同士を物理的・心理的に隔離する必要がある場合や、再発のリスクが高い職場環境を避ける目的で実施されます。
- 出勤停止・減給
一定期間の謹慎措置として用いられます。ハラスメントの重大性を周囲に示し、本人の内省を促す効果があります。
- 懲戒解雇・諭旨解雇
明らかに悪意がある、複数回の指摘を受けてなお改善が見られない、もしくは刑事罰に該当するような重大な行為に対して適用されます。企業としての毅然とした姿勢を示す措置です。
処分を決定する際には、就業規則や懲戒規定に照らした合理性と、本人の弁明機会の確保(手続的公正)が不可欠です。
また、単に「罰を与える」だけでは、根本的な再発防止にはつながりません。むしろ、加害者がなぜ自分の行動が問題であったのかを正しく理解しなければ、同様の行為が再び起こる可能性は高くなります。
そのため、以下のような教育的な指導も積極的に取り入れるべきです。
- 個別面談による行為の振り返り
産業医や人事担当者、または外部カウンセラーと共に、言動の背景・動機・影響などを整理します。
- ハラスメント研修への参加
「なぜ相手が傷ついたのか」「どうすれば防げたのか」などを事例とともに学び、認知のズレを是正します。
- 行動目標の設定と評価
再発を防止するための具体的な行動計画を本人に立てさせ、一定期間ごとに振り返るしくみを設けます。
処分が決定したあとは、必要に応じて関係者や周囲の社員に適切な説明を行うことも大切です。ただし、加害者のプライバシーや名誉も守る必要があるため、「何が起きたか」ではなく「会社として再発防止策を講じた」旨を伝えるにとどめるのが一般的です。
説明を怠ると、職場内で誤解や噂が広がり、「企業は何も対応していない」といった不信感を生む恐れもあります。
再発防止のためのフォローアップ
加害者への処分や指導が一通り完了したあとも、そこで対応が終わりではありません。表面的な対応で終わってしまえば、本人の行動は変わらず、被害者や周囲の不安も拭えません。また、再発防止は個人の内省だけではなく、職場全体の空気や関係性、組織文化の見直しといった視点も欠かせません。
なぜフォローアップが必要なのか?
加害者本人は、「処分を受けた=もう終わった」と捉えがちですが、実際にはその後の言動や周囲との関係構築が極めて重要です。放置しておくと、以下のような問題が起こりやすくなります。
- 表面的には反省しているが、内面では不満や逆恨みが残っている
- 同様の価値観・行動を職場内で再び繰り返す
- 周囲が気を遣いすぎて、チーム全体のコミュニケーションがぎこちなくなる
- 被害者や第三者が安心して働けない状態が続く
こうした状況を防ぐために、計画的・継続的なフォローアップが必要不可欠なのです。
効果的なフォローアップの例
✔ 定期的な個別面談・産業医による心理的フォロー
加害者と定期的に1on1面談を行い、現在の職場での様子や気持ちの変化、行動の変化を確認します。とくに、産業医や社外カウンセラーによる面談を組み込むことで、本人のストレス反応や対人関係の問題に専門的な視点でアプローチできます。
また、「どうすれば自分の行動を変えられるか」「チームにどう貢献できるか」といった前向きなテーマを話し合うことで、反省から改善へのステップを踏む手助けとなります。
✔ ハラスメント防止に関する研修・教育の再受講
加害者本人に対し、ハラスメントの基礎知識・法的リスク・周囲への影響をあらためて学ばせることも効果的です。再発防止に向けては、「自分の言動がどう受け止められるか」という“他者視点”を身につけることが重要となります。
また、加害者だけでなく職場全体へのハラスメント防止研修をあわせて実施することで、組織としての姿勢や行動指針を共有することができます。
✔ コミュニケーション環境の見直し・改善
再発防止には、加害者個人の行動変容と同時に、職場内のコミュニケーション環境の改善も欠かせません。たとえば次のような取り組みが有効です。
- チーム内での「報連相(報告・連絡・相談)」の促進
- 日常的な対話の場(朝礼や1on1など)を増やす
- 心理的安全性に配慮したフィードバック文化の構築
- ハラスメント通報・相談窓口の継続的な周知と利便性向上
こうした土台づくりにより、「誰かがおかしな言動をしても、周囲が声を上げやすい職場風土」を育てることができます。
一度限りの対策や一過性の研修では、行動の定着は難しく、元に戻ってしまう可能性もあります。だからこそ、フォローアップは「仕組み」として組み込み、半年・1年スパンで継続的に進める計画性が重要です。
加害者をただ“罰する”のではなく、「どうすれば成長と改善を促せるか」「職場に貢献できる人材として再起できるか」という視点でサポートすることが、結果的に職場全体の風土を健全な方向へと導くことになります。
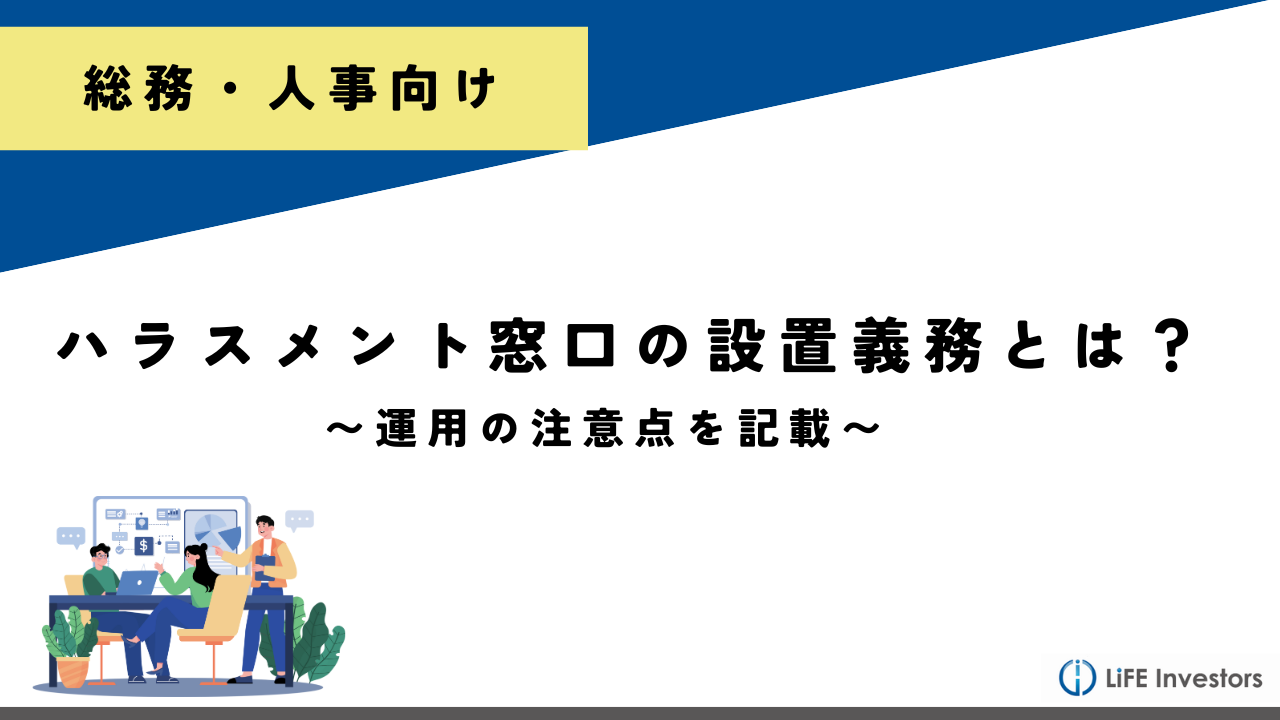
まとめ
ハラスメント加害者への対応は、感情的になりやすく、判断を誤ると組織全体に大きな影響を及ぼします。しかし、冷静で公平な対応を心がけることで、被害者の安心感だけでなく、加害者への改善支援や職場風土の向上にもつながります。
「加害者=排除すべき存在」と捉えるのではなく、「組織として再発を防ぎ、誰もが働きやすい職場をつくるためにどうすべきか」を軸に対応を考えることが重要です。
ハラスメント対応でお悩みの方へ:産業医の専門的サポートを活用しませんか?
ハラスメント問題は、感情・人間関係・法的リスクなど複雑な要素が絡みます。特に加害者対応においては、心理面への配慮や再発防止策まで含めた専門的な対応が求められます。
そんなときこそ、外部の産業医による支援が有効です。
ライフインベスターズでは、このようなハラスメントに関する課題を抱える法人様に対しても、産業保健の領域からサポートを行っております。
- 加害者・被害者双方への適切な対応アドバイス
- 職場改善につながる面談・指導
- 管理職向けのハラスメント研修の企画・実施
- 労基署や法律事務所と連携したリスク対応支援
無料相談や資料請求はいつでも可能です。専門家の知見を活用しながら、従業員が安心して働ける環境づくりを目指しましょう。
【関連リンク】
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2019_manual.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/001052058.pdf