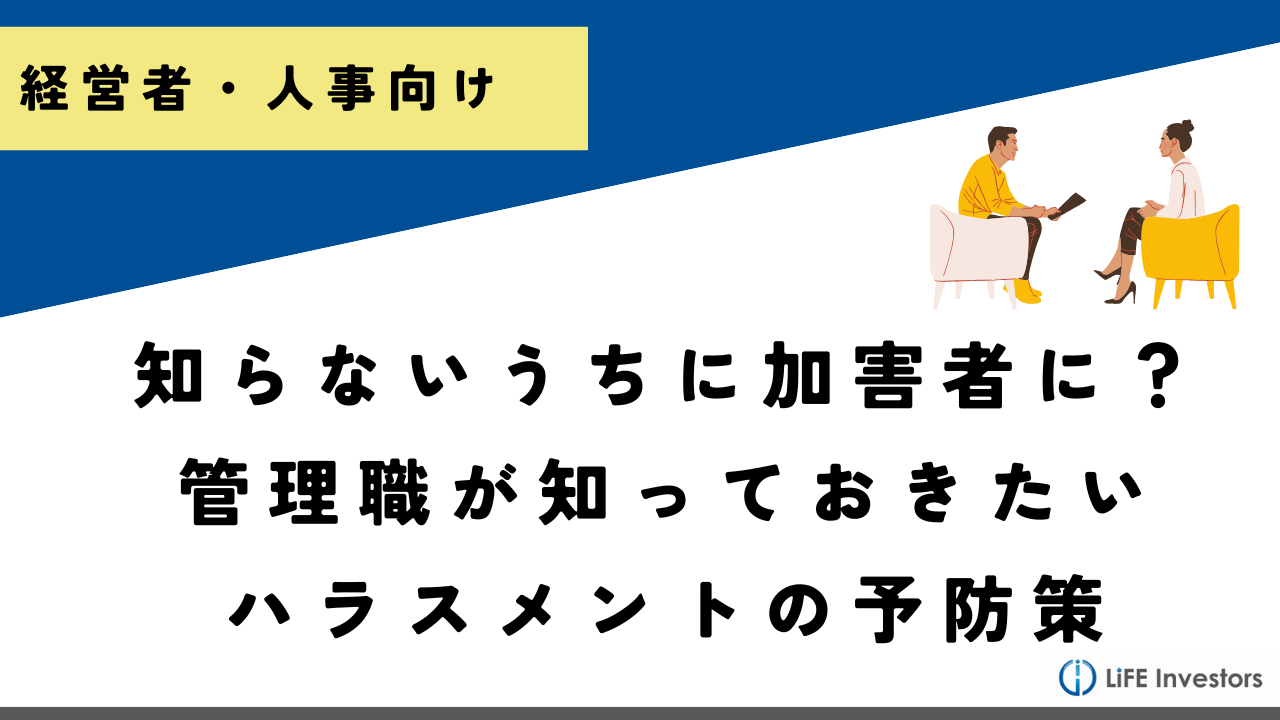この記事はこのようなお悩みをお持ちの方に向けて書いています。
・部下との接し方に不安を感じている
・ハラスメントを起こさないために自分の言動を見直したい
・「加害者」として指摘されないためのリスク管理をしたい
職場での何気ない一言や、指導のつもりの発言が、「ハラスメント」と受け取られてしまうことが増えています。特に管理職やマネージャーといった立場にある方は、部下との距離感に悩むことも多いのではないでしょうか。
「部下のために厳しく言ったのに」「みんなに言っているつもりだった」といった思いは、残念ながら相手には伝わらず、結果として加害者とみなされてしまうケースも少なくありません。
この記事では、管理職が無意識にハラスメントを行ってしまわないために必要な知識と、具体的な予防策について解説します。
ハラスメントの基本と「加害者」とされるリスク
まず押さえておきたいのは、「ハラスメント」とは、受け手が不快に感じたかどうかが大きな判断基準になる、という点です。意図の有無にかかわらず、相手が「嫌だ」と感じれば成立する可能性があるのがハラスメントの特徴です。
主なハラスメントには、以下のような種類があります。
- パワーハラスメント(パワハラ):職務上の地位を利用した不適切な言動
- セクシャルハラスメント(セクハラ):性的な言動に関するもの
- マタニティ・ハラスメント(マタハラ):妊娠や育児に関連する差別的言動
「自分には関係ない」と思っていても、何気ない指摘や発言が部下にとってはプレッシャーや苦痛になることがあります。そして、被害を訴えられた場合には、自分が“加害者”として扱われることになりかねません。
それぞれのハラスメントについては以下の記事もご参照ください。
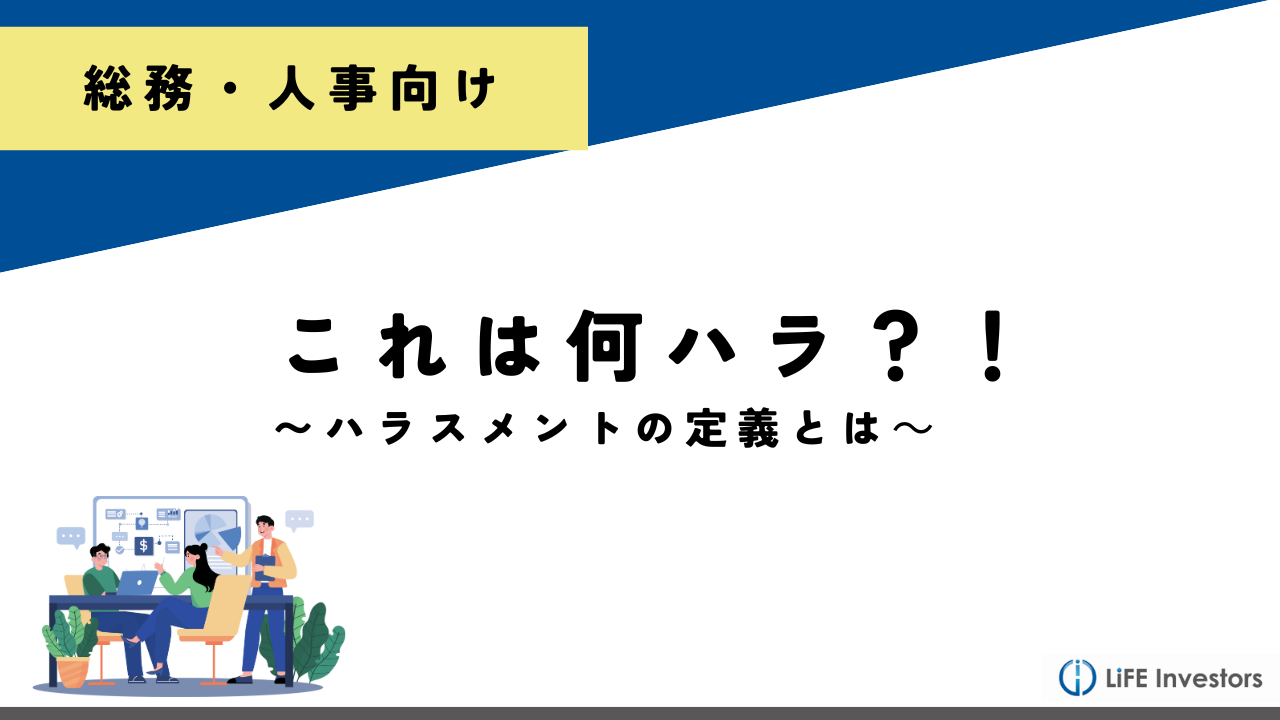
なぜ管理職が加害者になりやすいのか?

管理職は、部下の指導や評価、業務の指示などを行う「権限」を持っています。この権限は本来、組織を円滑に運営するためのものですが、使い方を誤ると“支配”や“強制”と受け取られる危険性があります。
また、以下のような理由から、管理職が加害者になるリスクが高まります。
- 忙しさから、丁寧なコミュニケーションを省略しがち
- 昔の価値観(「これくらい当たり前」「昔はもっと厳しかった」)が残っている
- 同じ部下に繰り返し注意をしてしまう
- ハラスメントの定義をよく知らないまま指導を行っている
自分では「正しい指導」と思っていても、それが精神的な圧力や人格否定と取られることがあるため、十分な注意が必要です。
無意識の言動がハラスメントになる例
「そんなつもりはなかった」「ただの冗談だったのに」──多くのハラスメントは、こうした無意識の一言から始まります。管理職という立場上、日々のコミュニケーションや指導の中で、自分では気づかぬうちに部下を傷つけてしまっていることもあります。
ここでは、ハラスメントと受け取られやすい典型的な言動をいくつかご紹介します。
人格を否定する言い方
業務上の指導をする際に、ミスや遅れに対して感情的に叱責してしまう場面は少なくありません。しかし、「使えない」「ダメだ」「センスがない」といった言葉は、業務上の改善点ではなく個人の価値そのものを否定する言い方になり、深く傷つける原因になります。
業務に関係のない外見や年齢に関するコメント
「若いのにしっかりしてるね」「その服、派手じゃない?」といった言葉も、言い方やタイミングによってはセクハラやパワハラと受け取られることがあります。特に年齢、体型、服装、髪型などは個人の属性に関わるデリケートな話題のため、注意が必要です。
異性の部下への過度な距離の近さやプライベートな質問
飲み会の席やちょっとした休憩中に「彼氏(彼女)いるの?」「家どこなの?」といった質問をしていませんか?聞く側に悪気がなくても、異性からの個人的な関心がプレッシャーや不快感として受け取られることがあります。また、ボディタッチや必要以上の接近もNGです。
有給取得や時短勤務に対する否定的な発言
「また休み?」「時短で帰れていいね」などの言葉は、制度を利用している社員に対して「迷惑をかけている」と思わせる要因になり得ます。これはマタニティハラスメント(マタハラ)やケアハラスメント(ケアハラ)とされる可能性がある行為です。
これらの発言は、言った側が軽い気持ちであっても、受け手の立場や心情、職場の雰囲気によって「ハラスメント」とみなされるリスクがあります。
特に、立場の強い管理職が言うことで、相手は反論しにくくなり、心理的負担が蓄積しやすくなります。「これは指導のつもり」「ただの雑談だった」では済まされないこともあるのです。
加害者にならないための予防ポイント
では、加害者とならないためにどのような行動を意識すれば良いのでしょうか。以下のポイントを習慣化することで、加害者にならないための土台を築くことができます。
1. ハラスメントの基礎知識を学ぶ
まず何よりも大切なのは、「どこからがハラスメントになるのか」という基本的な知識を持つことです。自分の常識と世の中の基準がズレていても、それに気づかなければ行動は変わりません。
たとえば、以下のような誤解は非常に多く見られます。
「指導だから厳しく言っても構わない」
「仲がいいから冗談で言っても問題ない」
「昔はこれが普通だった」
これらはいずれも、現代のハラスメント定義では通用しない可能性があります。厚生労働省のガイドラインや企業のコンプライアンス研修などを通じて、最新の情報にアップデートしておきましょう。
2. 日頃の言動を振り返る習慣を
忙しい日々の中でも、意識的に自分の言動を振り返る時間を持つことは、ハラスメント予防に非常に効果的です。
たとえば、以下のようなチェックを日課にしてみてください。
- 今日は部下に対して感情的な言い方をしていなかったか
- 指導の内容が個人攻撃になっていなかったか
- 部下が明らかに気まずそうにしていなかったか
1日1分でも振り返る時間を持つことで、「無自覚のまま過ぎていた不適切な言動」に気づくきっかけになります。こうした内省の習慣は、信頼される上司への第一歩でもあります。
3. 一人ひとりに配慮した対応を心がける
部下への接し方において、「全員に同じように接しているつもり」が、時にハラスメントの温床になることがあります。なぜなら、部下一人ひとりが置かれた状況や価値観、感じ方は異なるからです。
例えば、同じ指摘でも
- Aさんには建設的に受け取られる
- Bさんには強く否定されたように感じられる
というように、受け手の特性によって印象が大きく変わることがあります。大切なのは、「平等=一律に接すること」ではなく、「公平=個別の事情に配慮すること」という視点です。
4. 指導とハラスメントの違いを明確に
部下の育成や業務改善を目的とした指導は、管理職の重要な役割です。しかし、これが感情に任せた叱責や個人への攻撃に変わってしまうと、指導とは言えなくなります。
良い指導とハラスメントを分けるポイントは、以下の通りです。
| 項目 | 良い指導 | ハラスメントとされる指摘 | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 業務の改善、スキル向上 | 怒りの発散、人格否定 | |
| 内容 | 具体的な行動に対する指摘 | 曖昧な批判、感情的な言葉 | |
| トーン | 冷静で落ち着いた態度 | 怒鳴る、無視する、皮肉を言う |
指導の目的が「相手を育てる」ことになっているかどうかを、常に意識しておきましょう。具体的で建設的なフィードバックが、部下との信頼関係を深めるカギになります。
職場全体でハラスメントを防ぐために
個人の意識だけでなく、職場全体でハラスメントを防ぐ環境を整えることも重要です。たとえば
- 定期的なハラスメント研修の実施
- 外部相談窓口や社内相談体制の整備
- 上司同士でのケース共有やロールプレイ
こうした仕組みがあれば、管理職も安心して部下に接することができ、「気づかぬ加害者」を防ぐ助けになります。
以下の記事で詳しく解説しているので、そちらもぜひご参照ください。
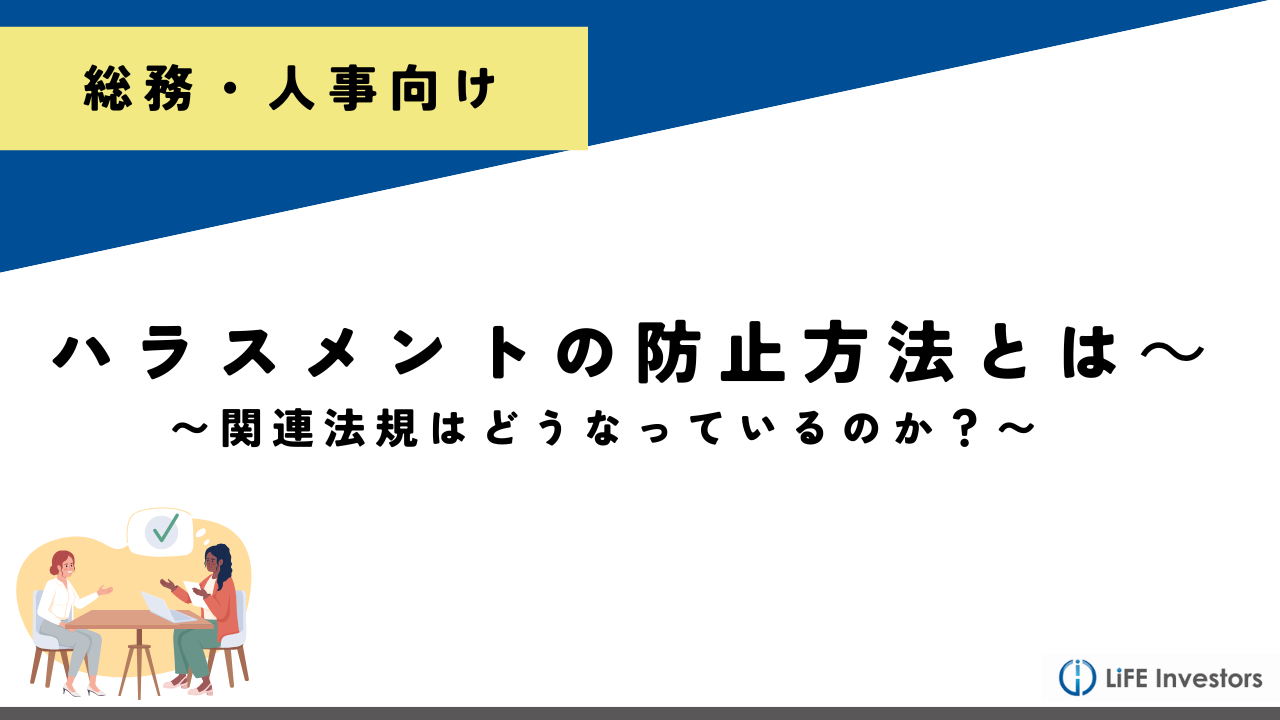
まとめ:信頼される管理職であるために
管理職は、部下にとって身近な存在であると同時に、強い影響力を持つ存在です。そのため、日常的な言動がハラスメントと受け取られるリスクを常に意識する必要があります。
大切なのは、部下との信頼関係を築くこと。正しい知識と冷静な対応を身につけることで、ハラスメントの加害者とならず、職場の安心と生産性を両立させることができるでしょう。
専門家のサポートで、ハラスメントのない職場づくりを
ハラスメントを防ぐためには、管理職一人ひとりの意識と行動だけでなく、組織としての支援体制や教育の仕組みも不可欠です。
とはいえ、「どうやって社内研修を始めればいいのか分からない」「外部の専門家に相談したい」と感じることもあるでしょう。そんなときは、産業医派遣サービス「ライフインベスターズ」をご活用ください。
弊社では、このようなハラスメントに関する課題を抱える法人様に対しても、産業保健の領域からサポートを行っております。
- ハラスメント防止に関する管理職向け研修・面談の実施
- ハラスメント事案の対応に関する専門的なアドバイス
- 再発防止のための職場環境改善支援
- 加害者・被害者双方のメンタルケア対応
無料相談や資料請求も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。
【関連リンク】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html