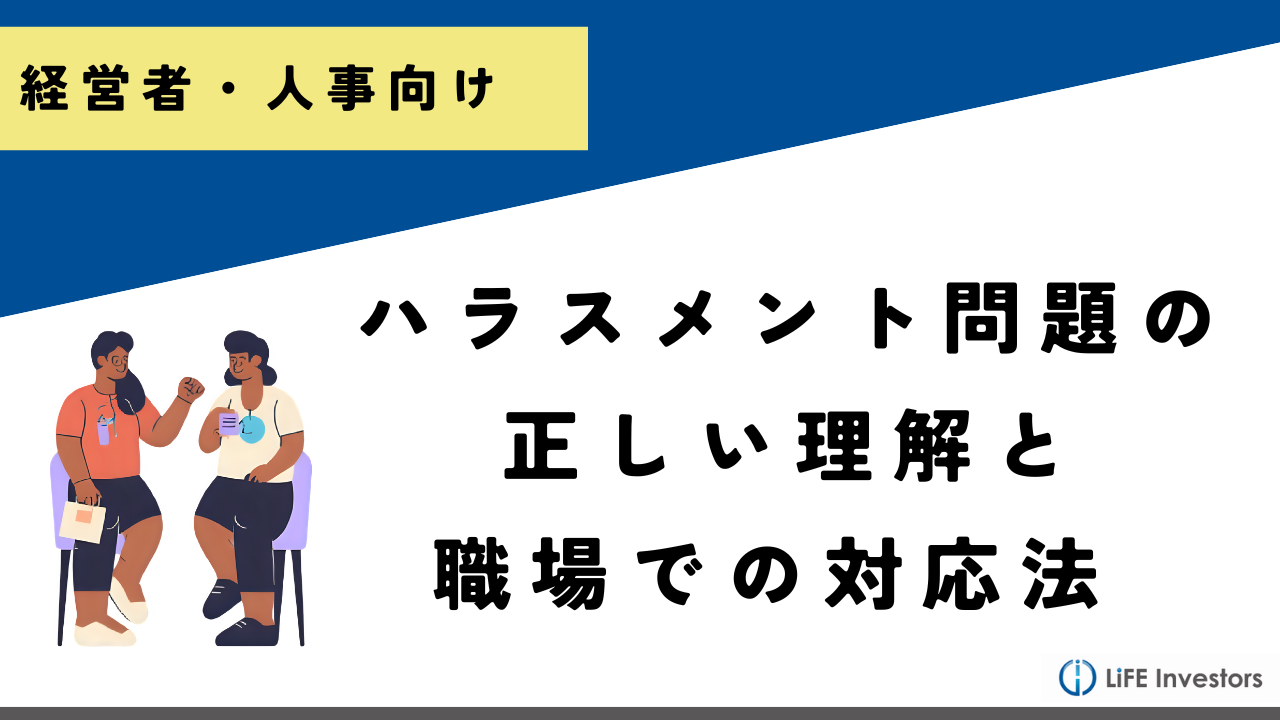この記事はこのような方に向けて書いています。
・ハラスメントの相談が増えていて対応に不安を感じている人事担当者
・社内のハラスメント防止体制を見直したいと考えている労務管理者
・「何がハラスメントになるのか」を正しく把握しておきたい方
「それって本当にハラスメントなの?」
「本人が気にしていなければ問題ないのでは?」
こうした認識は、もはや通用しない時代になりました。ハラスメントは企業のコンプライアンスリスクであり、対応を誤ると、組織の信頼失墜や人材流出、法的責任につながる深刻な問題です。
企業に求められるのは、「起きてから対処する」ではなく、「起きる前に防ぐ」姿勢です。特に人事・労務部門は、職場のハラスメントリスクに対して最前線で向き合う役割を担っています。
この記事では、ハラスメント問題の基礎から、具体的な対応策、そして再発防止のための体制づくりまで、人事労務の立場から実践的に解説します。
ハラスメントの種類と定義
ハラスメントとは、相手に対して不快感や苦痛を与える行為や言動のことを指します。意図的であれ無意識であれ、相手が嫌がっていたらハラスメントになります。日本語で言うところの「嫌がらせ」「いじめ」にあたるものです。
代表的なものには以下があります。
- パワーハラスメント(パワハラ)
職権を背景にした精神的・身体的攻撃、業務上の過大・過小な要求など
- セクシュアルハラスメント(セクハラ)
性的な言動により相手を不快にさせる行為
- マタニティハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産・育児休業等を理由とした不利益な取扱いや嫌がらせ
厚生労働省の定義によれば、「相手が不快に感じたかどうか」が判断の基準となるため、「冗談のつもりだった」「悪気はなかった」は通用しません。
詳しくは以下の記事をご参照ください。
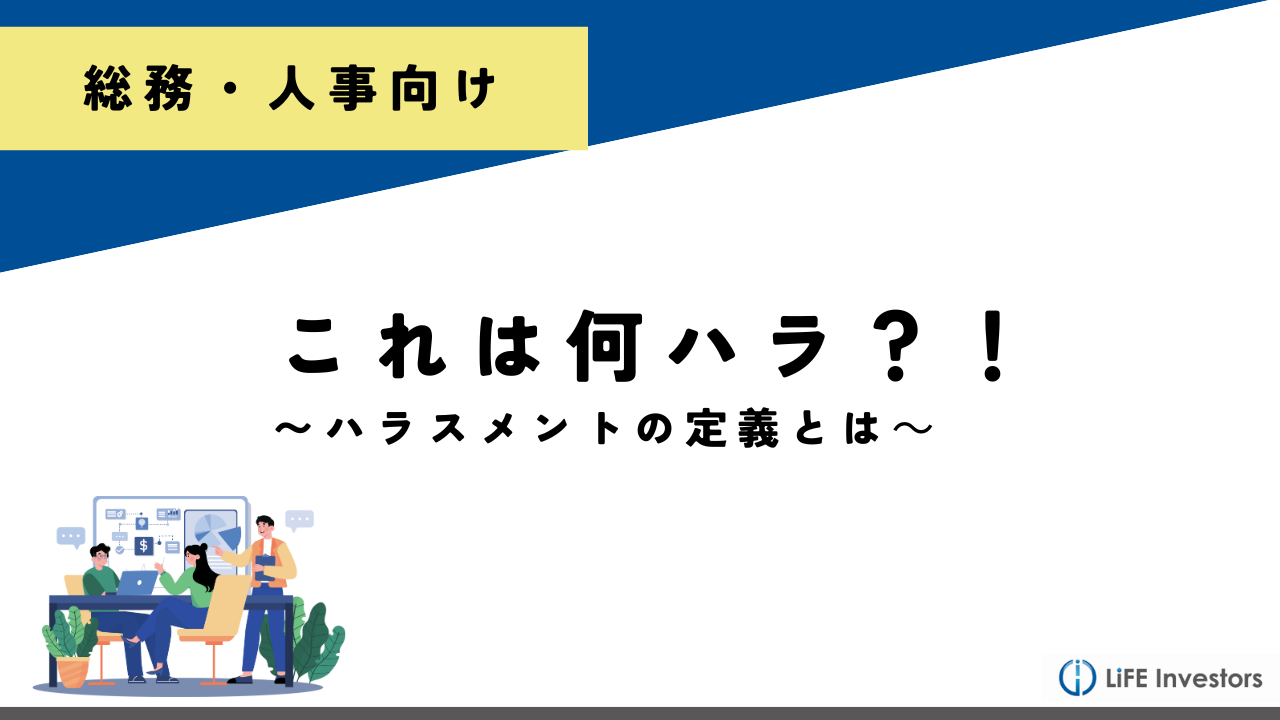
ハラスメントを放置するとどうなる?
人事労務担当者は、ハラスメントを「見逃さない」「適切に対処する」責任を負っています。もし対応が遅れたり、不適切な処理を行ったりした場合、以下のようなリスクが生じます。
- 被害者のメンタルヘルス悪化や離職
- 加害者・組織に対する訴訟・労基署対応
- 社内外への信頼失墜や風評リスク
- 管理職や企業への損害賠償請求の可能性
特に、「相談窓口があるだけ」「就業規則に書いてあるだけ」では不十分です。制度が機能し、安心して声を上げられる環境をつくることが求められます。
苦情・相談を受けたときの対応

ハラスメントの相談を受けた際には、初期対応が非常に重要です。以下のステップを意識しましょう。
1. 当人に対する事実の聴き取り
まずは感情的にならず、被害者の話を否定せずに受け止める姿勢が大切です。誰が・いつ・どこで・何を・どう感じたのかを、記録として残しましょう。
2. 関係者からの聞き取り
被害者・加害者の双方から話を聞き客観的な事実確認を進めます。可能であれば第三者的な立場での同席や、複数人での対応が望ましいです。
3. 適切な保護措置をとる
調査中も含めて、被害者と加害者が接触しないように配慮したり、被害者の勤務体制を一時的に見直すなどの対応が求められます。
再発を防ぐために企業が整えるべき体制
ハラスメントを「一過性の問題」で終わらせないためには、再発防止に向けた仕組みづくりが不可欠です。
1.明文化されたハラスメント防止方針と行動規範の策定
まず必要なのが、ハラスメントを許容しないという企業の明確なスタンスを示すことです。
企業としてのハラスメント防止方針は、経営層のメッセージとして全従業員に伝えることが重要です。また、抽象的な理念だけでなく、
- どのような行為がハラスメントに該当するのか
- 何が問題行動とされるのか
- 加害行為があった場合の処分規定
といった具体的な行動規範や判断基準まで明記することで、現場での混乱を防げます。
このようなガイドラインを明文化し、就業規則や社員ハンドブックなどに組み込むことで、職場全体に共通認識が生まれ、抑止効果も期待できます。
2.匿名でも相談できる社内窓口の設置
相談窓口の設置は多くの企業が行っていますが、実際に活用されるかどうかは別問題です。大切なのは、「安心して利用できる仕組み」をつくることです。
特に効果的なのは、匿名での相談が可能な窓口の併設です。これにより、
- ハラスメントを受けているが、報復が怖くて言い出せない
- 加害者が上司や経営層であり、相談先が限られる
- 本人も「これがハラスメントかどうか分からない」状態で相談したい
といったケースでも、声を上げやすくなります。
また、社外の第三者機関と連携した外部窓口も有効です。信頼性と中立性が担保されることで、相談件数が増える傾向にあります。
3.管理職・一般社員向けの定期研修の実施
ルールを作るだけではハラスメントは防げません。現場の一人ひとりが“自分ごと”として理解し、行動を変えていくことが求められます。
そのために有効なのが、年1回以上の定期的な研修の実施です。
- 管理職には、部下の言動に対する気づきや、指導とハラスメントの境界線に対する理解
- 一般社員には、被害者・傍観者・加害者にならないための心構えや対応方法
といった役割別の内容設計が効果的です。
研修では、判例や実例を交えたケーススタディやロールプレイを通じて、具体的な判断力・対応力を養うことが重要です。
4.相談・通報者への不利益取扱いの禁止明記
ハラスメントの防止において、最も重要かつデリケートなのが、「声を上げた人を守る」仕組みの整備です。
制度として明記すべきなのは、以下の点です。
- 通報者や相談者に対して、解雇・異動・減給などの不利益措置を一切行わないこと
- 通報内容の機密を保持し、関係者以外に一切漏らさない体制を整えること
- 二次被害(報復、無視、差別的扱いなど)への厳格な対応方針
これらを明文化し、全社員に周知徹底することが、相談のハードルを下げ、組織としての信頼性を高めることにつながります。
特に、人事部門はこうしたルールと運用の橋渡し役として、制度を機能させることが求められます。
ハラスメントを未然に防ぐ職場づくりとは
最終的に大切なのは、「そもそもハラスメントが起きにくい職場環境」をつくることです。
そのために人事・労務ができる取り組みとして、以下のようなものが効果的です。
- 日常的な1on1ミーティングによる風通しの良い関係づくり
- 働きやすさ・心理的安全性に関する定期アンケートの実施
- 管理職の「聴く力」や「気づく力」を高める研修
- 多様性・尊重をテーマにした社内イベントや広報活動
「うちは問題が起きていないから大丈夫」ではなく、「起きないように備える」のが現代の人事の責任です。
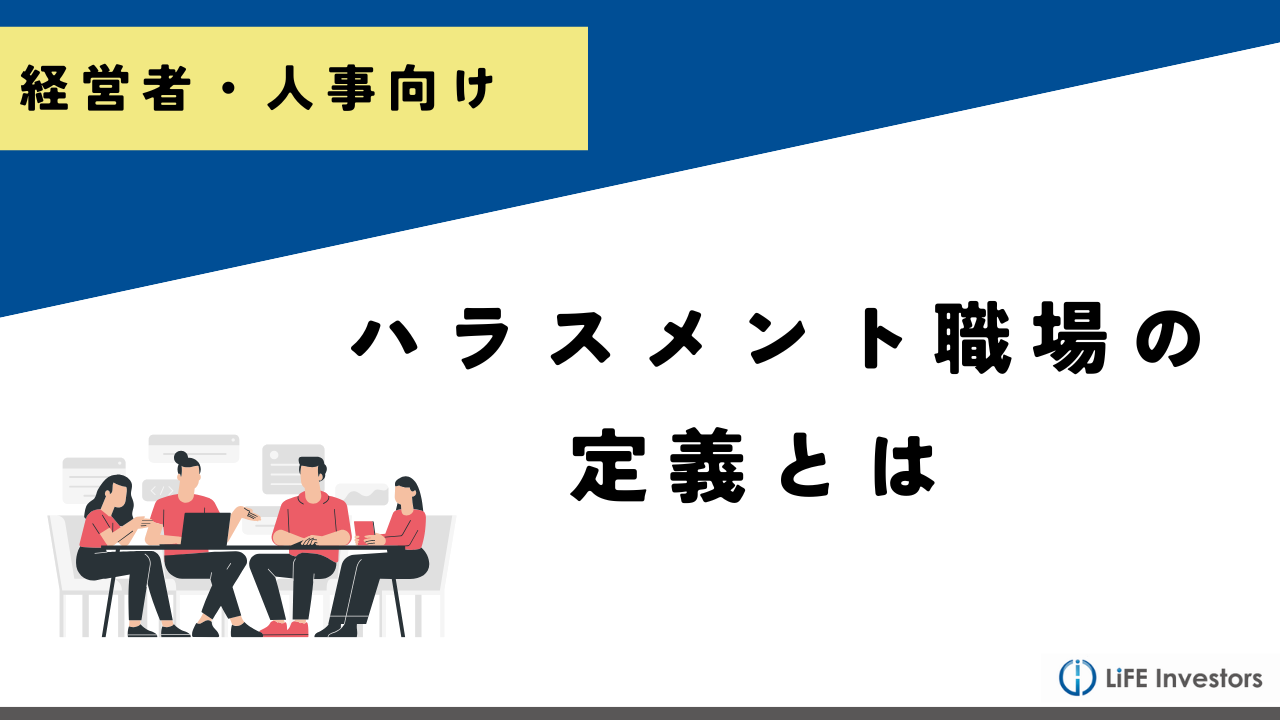
まとめ
ハラスメント問題は、一つの対応を誤るだけで組織全体に波及するリスクを孕んでいます。
これらの問題に対処するには、
- 定義や種類を正しく理解する
- 相談を受けたら迅速・丁寧に対応する
- 制度だけでなく、風土づくりにも力を入れる
といったポイントを押さえておくと良いでしょう。
人事労務部門が“最後の砦”として機能することで、従業員の安心感や信頼感が生まれ、結果的に健全な組織の運営につながります。
ハラスメント対応に専門家の力を
ハラスメント対策は、人事担当者だけで完結できるものではありません。制度の整備・初期対応・再発防止体制まで、専門的な知見と第三者的な視点が求められる場面も多くあります。
ライフインベスターズでは、このようなハラスメントに関する課題をお持ちの法人様に対しても、産業保健の領域からサポート行っております。
- 産業医を交えて社内のハラスメント相談体制を整えたい
- 産業医による客観的な立場からの助言がほしい
- 管理職向けの研修や制度設計を支援してほしい
こうした課題をお持ちの法人様は、ぜひ一度、弊社にご相談ください。
従業員一人ひとりが安心して働ける環境を整えることは、会社の持続的な成長につながります。信頼できる外部パートナーとともに、ハラスメントのない健全な職場づくりを進めていきましょう。
【関連リンク】
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/001466344.docx