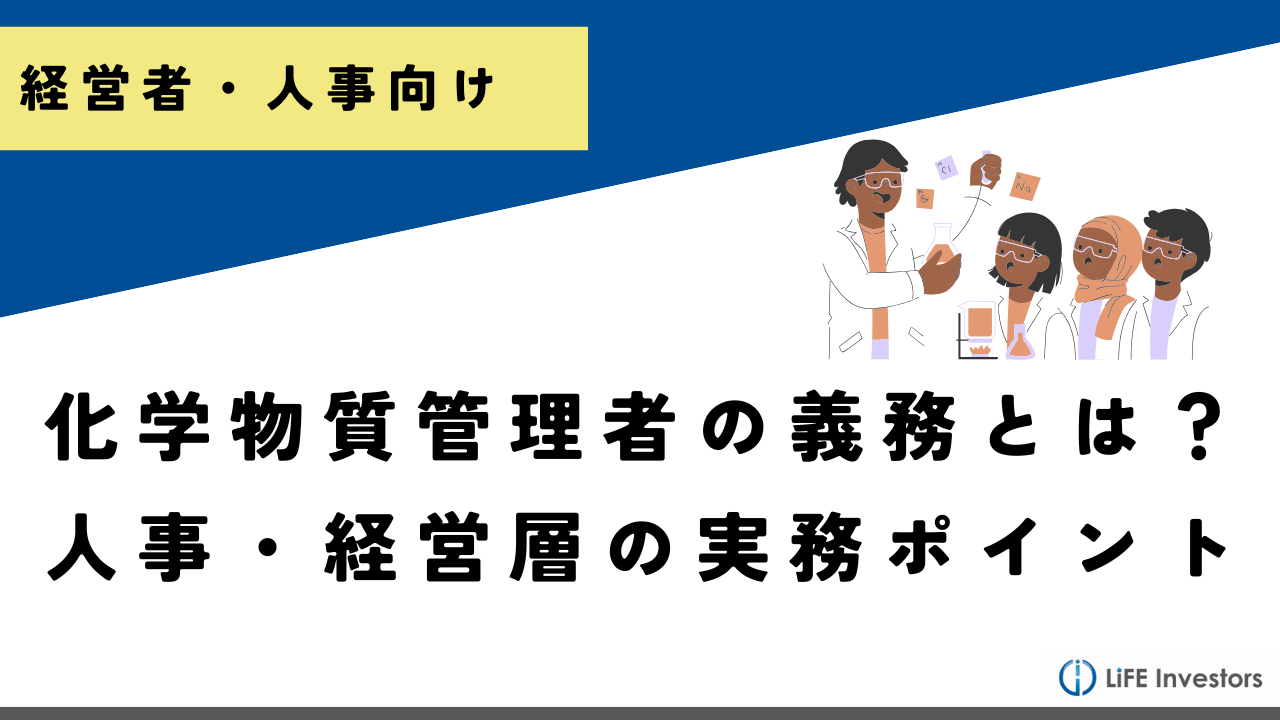この記事はこのような方に向けて書いています。
・製造業や化学薬品を取り扱う企業の人事労務担当
・安全衛生体制の強化に取り組む経営者・工場長
労働安全衛生法の改正により、すべての化学物質取扱い事業場において「化学物質管理者」の選任が義務化されました。
これまで限られた物質や業種だけに求められていた化学物質管理体制ですが、今後は「事業場の規模を問わず」対応が必要となります。
ただし現場では、「誰を選任すべきか」「どんな業務を行うのか」「どこまでが義務か」など、混乱も見られます。
この記事では、人事や経営層が知っておくべき化学物質管理者の法的義務と実務の要点をわかりやすく解説します。
化学物質管理者とは何か?
「化学物質管理者」とは、事業場における化学物質の管理に関する技術的事項を担う専門責任者です。
労働安全衛生法の改正により、2024年4月から次のような制度改革が実施されました。
- 従来の“個別規制型”から“自律的な管理”へ転換
- 全てのリスクアセスメント対象物(674物質→今後拡大予定)を扱う事業場で、選任が義務に
- 事業場の規模に関係なく適用
- 選任後は、氏名の掲示や必要な権限の付与が義務
特に重要なのは、単に名義上の選任ではなく、実務を遂行できる体制の整備が求められている点です。
義務化の対象と選任基準

対象事業場
以下に該当する事業場は、化学物質管理者の選任が義務です。
- リスクアセスメント対象物(表示・SDS交付義務物質)を製造または取り扱う事業場
- 事業場の規模を問わない
- ただし、一般消費者向けの製品のみを扱う事業場は除外
事業者は化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知しなければなりません。
また、事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、後述の職務をなしうる権限を与えなければなりません。
さらに、化学物質管理者の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。
選任の要件
化学物質管理者の選定条件は以下の通りです。
- 必要な知識と経験を有する者であること(事業者判断)
- リスクアセスメント対象物を製造する事業場では、厚労省指定の講習修了者のうちから選任すること(対象物の製造がない場合は、講習修了者または相当の知識・経験を有する者であれば可)
リスクアセスメント対象物を製造していないのであれば、特に資格要件はないので衛生管理者や作業主任者、作業環境測定士などが候補者となることが多いです。
化学物質管理者の主な職務内容
化学物質管理者の職務は、大きく分けて2つあります。
- 自社製品の譲渡・提供先への危険有害性の情報伝達に関する職務
- 自社の労働者の安全衛生確保に関する職務
具体的には以下のようになります。
1.ラベル表示とSDS交付の管理
事業者はリスクアセスメント対象物を含む製品をGHSに従って分類しラベル表示及びSDS交付をしなければなりません。化学物質管理者はその作業を管理します。
例:ラベル表示及びSDSの内容の適切性の確認等
2.リスクアセスメントの実施管理
リスクアセスメントの実施状況を管理します。具体的にはリスクアセスメントを実施すべき物質の確認、取扱い作業場の状況確認(当該物質の取扱量、作業者数、作業方法、作業場の状況等)、リスクアセスメント手法(測定、推定、業界・作業別リスクアセスメント・マニュアルの参照など)の決定及び評価、労働者へのリスクアセスメントの実施及びその結果の周知等を行います。
3.ばく露防止措置の検討・実施の管理
ばく露防止措置(代替物の使用、装置等の密閉化、局所排気装置又は全体換気装置の設置、作業方法の改善、保護具の使用など)の選択や使用について管理します。
4.労働災害時の応急対策・マニュアル整備
化学物質管理者は、実際にリスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合に適切に対応しなければなりません。そこで、実際に労働災害が発生した場合の対応、労働災害が発生した場合を想定した応急措置等の訓練の内容及び計画を管理します。 労働災害が発生した場合又は発生が懸念される場合(死傷病者の発生、有害物質への高濃度ばく露あるいは汚染など)の対応(避難経路確保、救急措置及び担当者の手配、危険有害物の除去及び除染作業、連絡網の整備、搬送先病院との連携、労働基準監督署⾧による指示が出された場合など)をマニュアル化し、化学物質管理者と他の担当者の職務分担を明確にします。マニュアル化した内容については、適切に訓練を行うことが望ましいでしょう。
5.リスク評価・対策の記録と保存
1 年を超えない期間ごとに定期的に記録を作成し、記録は3年間(がん原性物質は30年間)保存します。
6.労働者への周知・教育
1~4を実施するにあたっての労働者に対する必要な教育(雇入れ時教育を含む)の実施計画や教育効果の確認等を管理します。
人事・経営層が押さえるべき実務ポイント
化学物質管理者の選任が義務化された今、企業に求められるのは「選任した」という形式的な対応だけではありません。
実際に法令を満たす体制を整え、職場の安全衛生を継続的に維持・向上させる実効的な仕組みづくりが重要です。そのために、人事担当者や経営層には以下のようなアクションが求められます。
1.事業場でのリスクアセスメント対象物の洗い出し
まずは自社の事業場において、ラベル表示義務・SDS交付義務がある化学物質(リスクアセスメント対象物)をどれだけ取り扱っているかを把握することが出発点です。
この段階で、該当物質があるにも関わらず「対応が不要」と誤認しているケースも多く、制度対応が遅れる原因となります。
製造・加工・実験など、部門ごとに使用している薬剤や化学製品の一覧を精査し、対象物質とその使用状況を正確にリスト化しましょう。
2.選任対象者の確保と講習受講の計画
リスクアセスメント対象物を製造している事業場では、化学物質管理者として選任する者に厚生労働大臣が定めた講習の受講が求められます。
該当する従業員がいない場合は、早急に社内から候補者を選定し、講習スケジュールを確保する必要があります。
また、他業務と兼任させる場合の負荷や時間配分にも配慮が必要です。中小規模の企業では、外部の専門家を化学物質管理者の補佐役として活用する選択肢も有効です。
3.職務内容に応じた社内外体制の整備
化学物質管理者は多岐にわたる業務(ラベル管理、リスクアセスメント、災害対応、教育など)を担います。
すべてを一人で対応することが難しい場合は、業務ごとに役割を分担し、衛生管理者、安全管理者、作業主任者などと連携した体制を構築しましょう。
特にGHS分類やばく露測定など専門性の高い領域では、外部コンサルタントや専門機関との連携が実効性を高めるカギになります。
4.教育体制・マニュアルの見直し
法令では、化学物質に関する教育の実施とその計画の策定も化学物質管理者の重要な職務とされています。
そのため、現行の教育プログラムやマニュアルが最新制度に即しているかを確認する必要があります。
新入社員教育、現場担当者への定期研修、災害時対応訓練など、各段階に応じた教育体制を再構築することが求められます。
5.定期的な管理記録と保存体制の構築
法令では、リスクアセスメントの結果や災害対応訓練の記録、教育の実施状況など、多くの管理情報を一定期間保存する義務があります。
これらを手書きやExcelベースで場当たり的に管理していると、いざという時に対応できないリスクがあります。
そのため、デジタル管理ツールの導入やクラウドでの一元管理など、管理の属人化を避けた運用体制の整備が重要です。
GHS分類やSDS作成、ばく露測定など、専門知識が必要な分野については、厚労省も公式に外部専門家の活用を推奨しています。
法令対応だけでなく、実効性の高い安全衛生管理体制を構築するためにも、社外リソースを有効活用してみましょう。
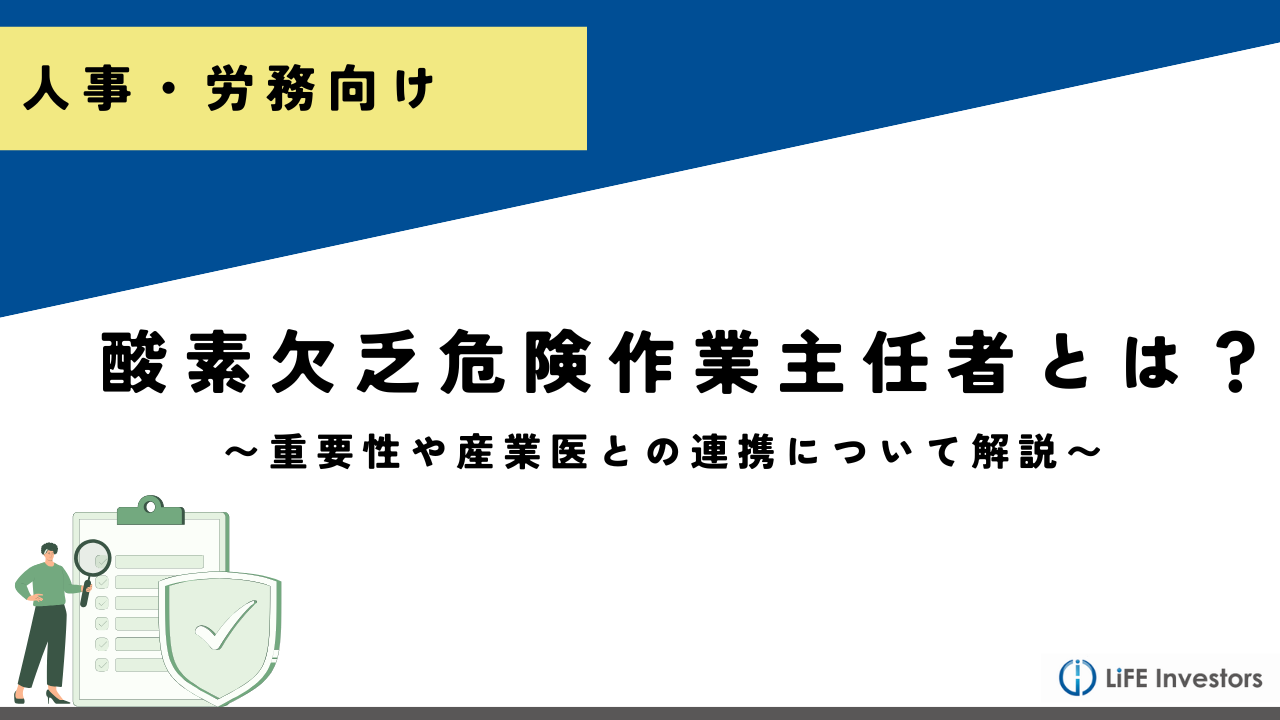
まとめ:今こそ“現場任せ”から“組織的管理”へ
化学物質管理者の制度は、単に選任するだけでなく、職務を果たせる体制整備と実務運用が不可欠です。
人事・経営層が制度の本質を理解し、早期に体制構築へ動くことが、労働災害の未然防止と企業の信頼性向上につながります。
まずは、自社の化学物質取り扱い状況を点検し、法令対応の第一歩を踏み出しましょう。
化学物質管理者の選任・体制構築に不安がある方へ
法改正により、化学物質管理者の選任や体制整備がすべての法人に求められるようになりました。しかし、
- 「誰を選任すればいいのかわからない」
- 「講習の受講や教育体制の準備が追いつかない」
- 「専門知識をもつ人材が社内にいない」
といったお悩みをお持ちの法人様も少なくありません。
ライフインベスターズでは、このような法人様に対しても、産業保健の領域からサポートを行っております。
「うちも対応が必要かもしれない」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【参考文献】