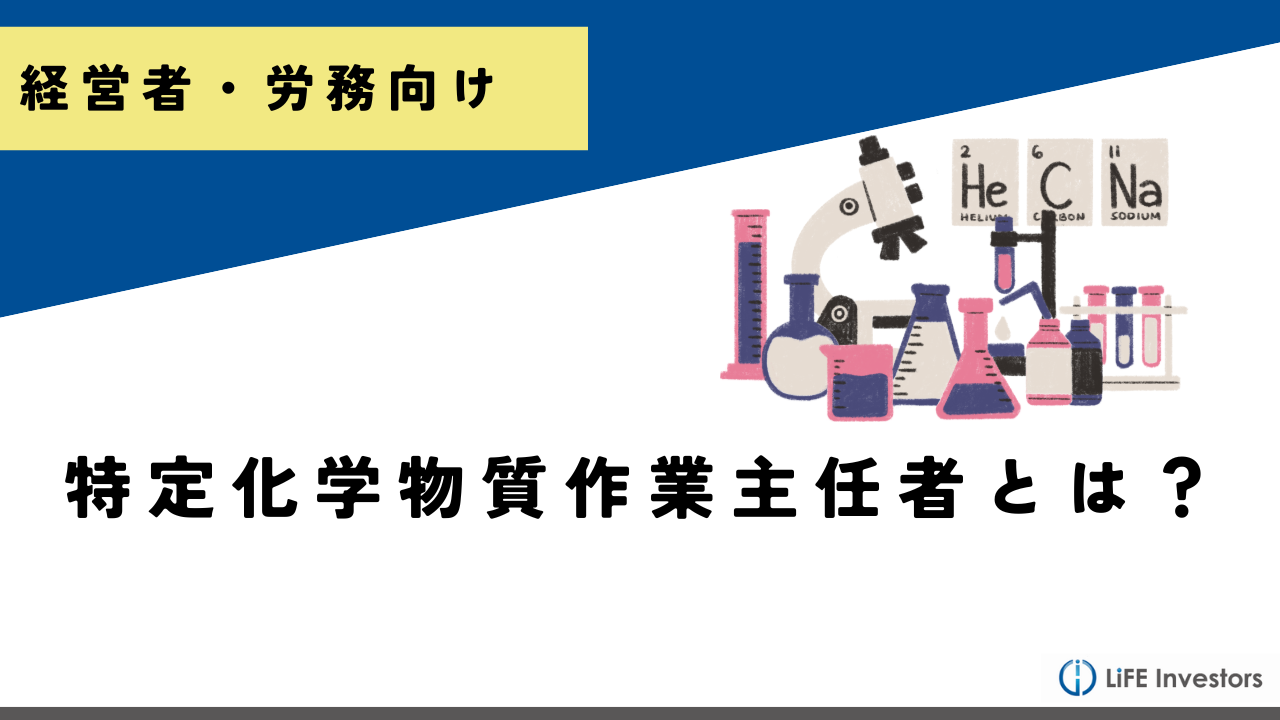この記事はこのような方に向けて書いています。
・製造業や化学関連業種の人事・労務担当をされている方
・職場で特定化学物質を取り扱う可能性があり、安全衛生管理を任されている方
・作業主任者の選任について正確に理解したい方
労働安全衛生法では、職場での健康被害を防ぐために、特定の作業には「作業主任者」の選任が義務づけられています。特に、有害性の高い特定化学物質を扱う現場では、「特定化学物質作業主任者」の配置が求められるケースが多くあります。
しかし、人事労務担当者の中には、「誰を選任すればいいのか」「どんな業務を担うのか」「資格取得の流れは?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定化学物質作業主任者の基本から、選任の義務や役割、資格取得のポイントまでをわかりやすく解説します。現場の安全を守るために、人事労務担当者として押さえておきたいポイントを整理していきましょう。
特定化学物質作業主任者とは?
特定化学物質には、ベンゼン・アニリン・塩素など、人体に有害な物質が含まれており、適切な管理を怠ると健康被害を引き起こす恐れがあります。これらを取り扱う作業環境では、有害な化学物質に曝露する危険が常に存在しており、健康被害のリスクを軽減するための知識と管理能力が不可欠です。
そのため、特定化学物質作業主任者は、有害性の高い特定化学物質を扱う作業現場において、安全衛生の観点から指導・監督を行うことが求められています。労働安全衛生法により、該当する作業を行う場合には、資格を持った作業主任者を選任することが義務づけられています。
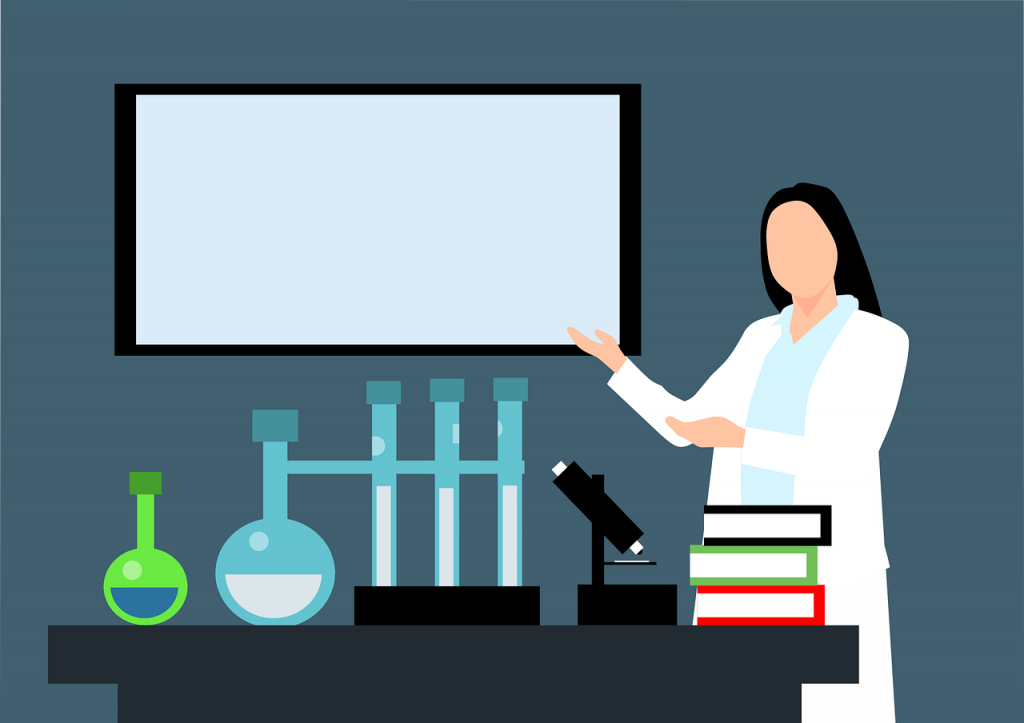
選任義務のある作業
後述の別表3で規定されている特定化学物質を製造または取り扱う業務を行う場合、特定化学物質作業主任者の選任が義務付けられています。
(作業主任者)
労働安全衛生法
第十四条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
(作業主任者を選任すべき作業)
労働安全衛生法施行令(抜粋)
第六条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 十八 別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業
別表第三
特定化学物質(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
1 ジクロルベンジジン及びその塩
2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
3 塩素化ビフエニル(別名PCB)
4 オルト―トリジン及びその塩
5 ジアニシジン及びその塩
6 ベリリウム及びその化合物
7 ベンゾトリクロリド
8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質1 アクリルアミド
2 アクリロニトリル
3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
3の2 インジウム化合物
3の3 エチルベンゼン
4 エチレンイミン
5 エチレンオキシド
6 塩化ビニル
7 塩素
8 オーラミン
8の2 オルト―トルイジン
9 オルト―フタロジニトリル
10 カドミウム及びその化合物
11 クロム酸及びその塩
11の2 クロロホルム
12 クロロメチルメチルエーテル
13 五酸化バナジウム
13の2 コバルト及びその無機化合物
14 コールタール
15 酸化プロピレン
15の2 三酸化二アンチモン
16 シアン化カリウム
17 シアン化水素
18 シアン化ナトリウム
18の2 四塩化炭素
18の3 一・四―ジオキサン
18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
19 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
19の2 一・二―ジクロロプロパン
19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
20 臭化メチル
21 重クロム酸及びその塩
22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
22の2 スチレン
22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
22の5 トリクロロエチレン
23 トリレンジイソシアネート
23の2 ナフタレン
23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
24 ニツケルカルボニル
25 ニトログリコール
26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
27 パラ―ニトロクロルベンゼン
27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
28 弗化水素
29 ベータ―プロピオラクトン
30 ベンゼン
31 ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
31の2 ホルムアルデヒド
32 マゼンタ
33 マンガン及びその化合物
33の2 メチルイソブチルケトン
34 沃化メチル
34の2 溶接ヒューム
34の3 リフラクトリーセラミックファイバー
35 硫化水素
36 硫酸ジメチル
37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質1 アンモニア
2 一酸化炭素
3 塩化水素
4 硝酸
5 二酸化硫黄
6 フエノール
7 ホスゲン
8 硫酸
9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
作業主任者の主な役割と責任
特定化学物質作業主任者は、現場での安全管理と作業者の健康保護を担う、いわば「安全の司令塔」です。業務範囲は多岐にわたりますが、大きく分けると以下のような役割が求められます。
- 作業前の点検と安全確認
作業開始前に設備や器具の状態、化学物質の保管状況を確認し、異常がないかをチェックします。万一、不備や危険要因が発見された場合は、作業を中断し、改善措置を指示する権限も持っています。 - 労働者への安全指導や教育
作業に従事する労働者に対し、特定化学物質の特性や危険性、適切な取り扱い方法を教育します。初めて業務に従事する人に対して、また、作業内容が変更になる場合には、必ず事前教育を実施することが求められます。 - 使用する保護具の管理と点検
防毒マスク、防護手袋、防護服などの保護具が正しく機能しているかを定期的に点検します。破損や劣化が見られる場合は速やかに交換し、作業者が正しい装着方法を理解しているかも確認します。 - 緊急時の対応マニュアル整備と指導
漏洩や暴露事故、火災などの緊急事態が発生した場合に備え、対応手順を整備します。また、避難経路や応急処置の方法を作業者全員に周知徹底することも主任者の責務です。 - 作業環境の改善提案
作業環境測定の結果や日常の点検で得られた情報をもとに、換気装置の改良、作業手順の見直し、化学物質の代替など、より安全な作業環境の構築に向けた改善提案を行います。
これらの業務は、単に机上の知識だけで行えるものではありません。現場に足を運び、作業状況を自ら確認し、適切な監督・指導を行う実践的なリーダーであることが求められます。
なお、企業側が作業主任者を「名義だけ」で選任し、実務を行わせない場合は、労働安全衛生法に基づく法令違反となる恐れがあります。これは重大な安全管理上の欠陥とみなされ、行政指導や罰則の対象となることもあります。
そのため、作業主任者の役割は形式的なものではなく、日々の現場で積極的に機能させることが、労働災害防止のために不可欠です。
資格取得の方法と要件
特定化学物質作業主任者になるには、労働技能講習会などが実施する技能講習を修了する必要があります。講習はおおよそ2日間で、学科中心の内容となっており、受講にあたって特別な実務経験は不要です。
講習修了後には、修了証が交付され、それにより主任者としての選任が可能となります。講習内容には以下のような項目が含まれます。
- 健康障害及びその予防措置に関する知識
- 作業環境の改善方法に関する知識
- 保護具に関する知識
- 関係法令
なお、講習のスケジュールや開催地は、地域によって異なるため、労働局や関連団体のウェブサイトで事前に確認しておくとよいでしょう。
配置・管理における実務ポイント
人事労務担当者にとって、特定化学物質作業主任者の配置・管理は単なる形式的な業務ではありません。「資格を持っている人を選ぶ」だけでは不十分であり、選任後も継続的なフォローと現場との連携が不可欠です。実務上は、以下のようなポイントを押さえておく必要があります。
- 有資格者が現場で実際に活動しているかを定期的に確認する
資格は持っていても、現場で監督・指導の役割を果たしていないケースがあります。毎月の安全パトロールや現場ミーティングへの参加状況をチェックし、主任者の実働を可視化しましょう。 - 異動や退職があった場合、代替の主任者を速やかに選任する
主任者が不在になると、作業そのものが法的に実施できなくなる場合があります。異動や退職が判明した時点で後任候補を確保し、業務が途切れない体制を整えることが重要です。 - 作業内容に応じた適切な教育や研修を継続的に行う
法令や化学物質の取扱基準は改正されることがあります。また、新しい作業手順や設備変更があれば、その都度主任者と作業者への教育が必要です。外部講習や社内研修の定期開催が効果的です。 - 労働基準監督署の立ち入り検査にも対応できるよう体制を整備する
検査では、主任者の選任届や資格証明書、点検記録、安全指導の実施記録などが求められます。書類や記録を日頃から整理・保管しておくことで、急な検査にも慌てず対応できます。
特に、現場と人事部門の連携が不十分な場合、名ばかりの主任者選任にとどまり、法令違反や労働災害につながる危険があります。これは企業の信用低下や行政処分のリスクを伴い、経営に大きな影響を与えかねません。
安全衛生管理は一部署だけの責任ではなく、企業全体で取り組むべき経営課題です。人事・総務部門が中心となり、現場責任者や産業医、安全衛生委員会と密に情報共有しながら、実効性のある管理体制を構築することが求められます。
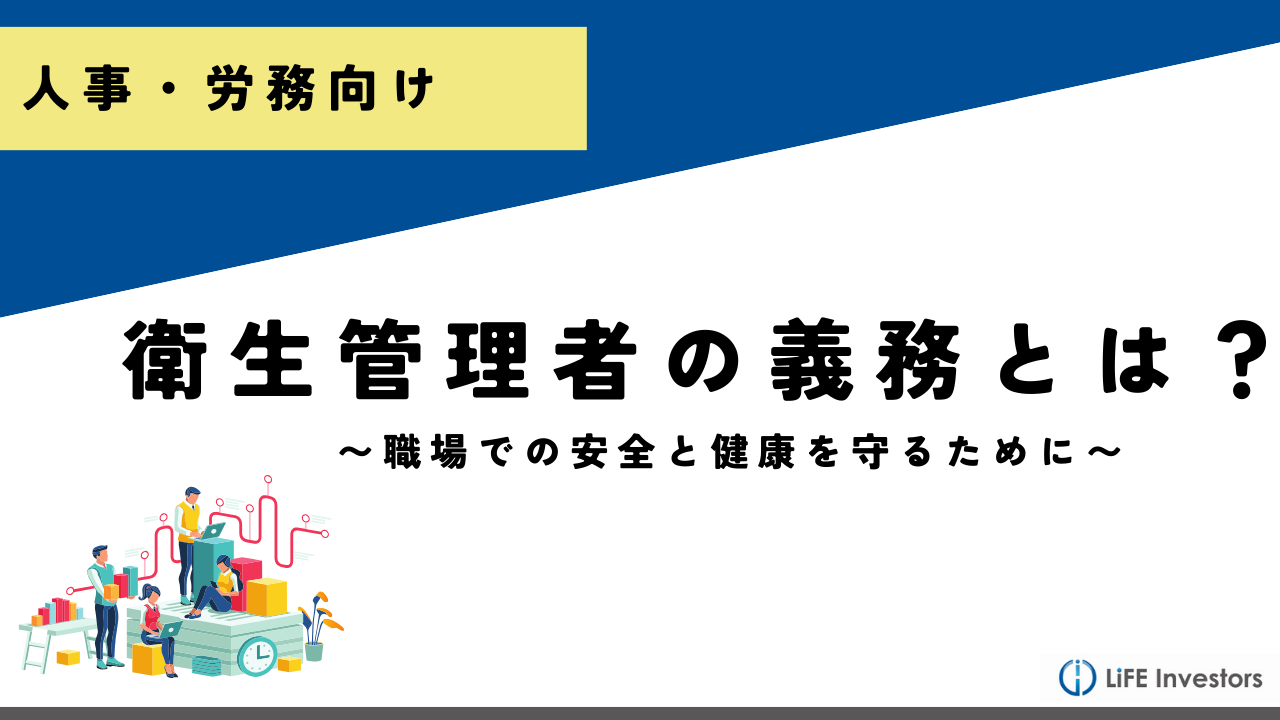
まとめ
特定化学物質作業主任者の役割と選任義務について、人事労務担当者が押さえておくべきポイントを解説してきました。
- 特定化学物質を取り扱う現場では主任者の選任が義務
- 主任者は安全管理・指導の要となる存在
- 資格取得には技能講習の受講が必要
- 実際の配置と継続的な管理が重要
現場の安全を守る体制づくりのために、まずは現状の確認から始めてみましょう。
安全衛生管理の体制づくりにお悩みの方へ
特定化学物質の取り扱いや作業主任者の選任には、専門的な知識と現場に即した対応が求められます。
「誰を選任すべきか迷っている」「産業医のサポートがない」といった課題をお持ちの法人様も少なくありません。
ライフインベスターズでは、経験豊富な産業医が職場ごとのリスクに応じた安全衛生体制の構築をサポートします。
特定化学物質に関する指導や、作業主任者の選任・教育に関するアドバイスも提供可能です。
- 安全衛生の体制を整えたい
- 産業医選任が必要か迷っている
- 特定化学物質を扱う作業に不安がある
このような方は、まずはお気軽にご相談ください。
貴社の状況に合わせた最適な対応策をご提案いたします。
【参考文献】