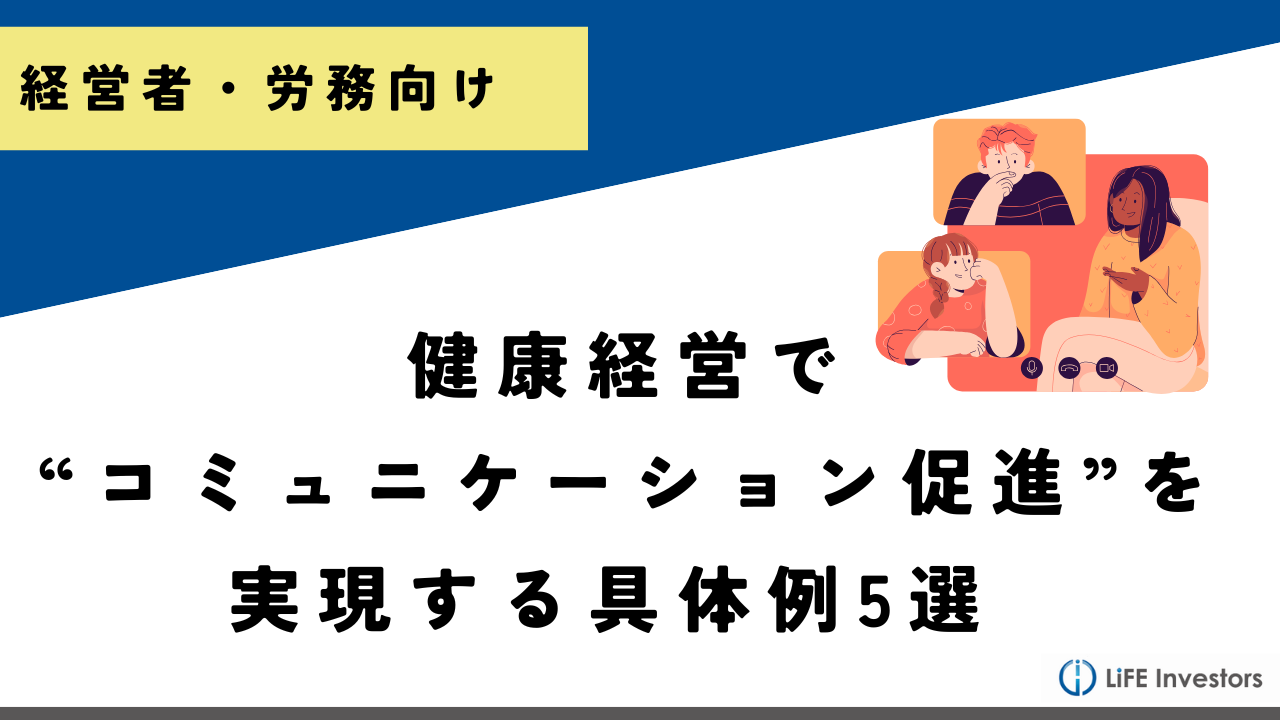この記事はこのようなお悩みをお持ちの方に向けて書いています。
・健康経営優良法人の認定を目指している
・「コミュニケーションの促進」の項目で何をすればよいか悩んでいる
・他社の実例を知りたい
健康経営の認定要件に含まれる「職場の活性化⑥ コミュニケーションの促進」という項目は、担当者にとって「何をすればよいのか分かりづらい」と感じられることの多いテーマです。しかし実際は、日常のちょっとした工夫で始められるものから、全社を巻き込む大掛かりな取り組みまで幅広い選択肢があります。ここでは、健康経営優良法人に認定された企業が実際に取り入れているコミュニケーション促進策を、難易度別に5つ紹介します。
職場の活性化⑥ 「コミュニケーションの促進」とは?
これは、経済産業省が定める「健康経営優良法人」認定項目のひとつで、従業員同士や上司・部下の間で活発なコミュニケーションを生み出すための取り組みを行っているかを評価するものです。
単なる“仲良しづくり”ではなく、
- 信頼関係の醸成
- 心理的安全性の確保
- メンタルヘルス不調の予防
- チームワークやエンゲージメントの向上
といった働きやすい職場づくりの基盤として重視されています。
職場でのコミュニケーション不足は、孤立感やストレスの増加につながり、うつ病などのメンタル不調や離職のリスクを高めます。一方で、安心して話し合える環境が整っている組織では、社員の健康度も業務パフォーマンスも高い傾向にあります。
健康経営優良法人の認定基準のこの項目には、“健康=身体的な健康だけでなく、心の健康や組織の健康も含む” という考え方が背景にあるのです。
認定を意識したポイント
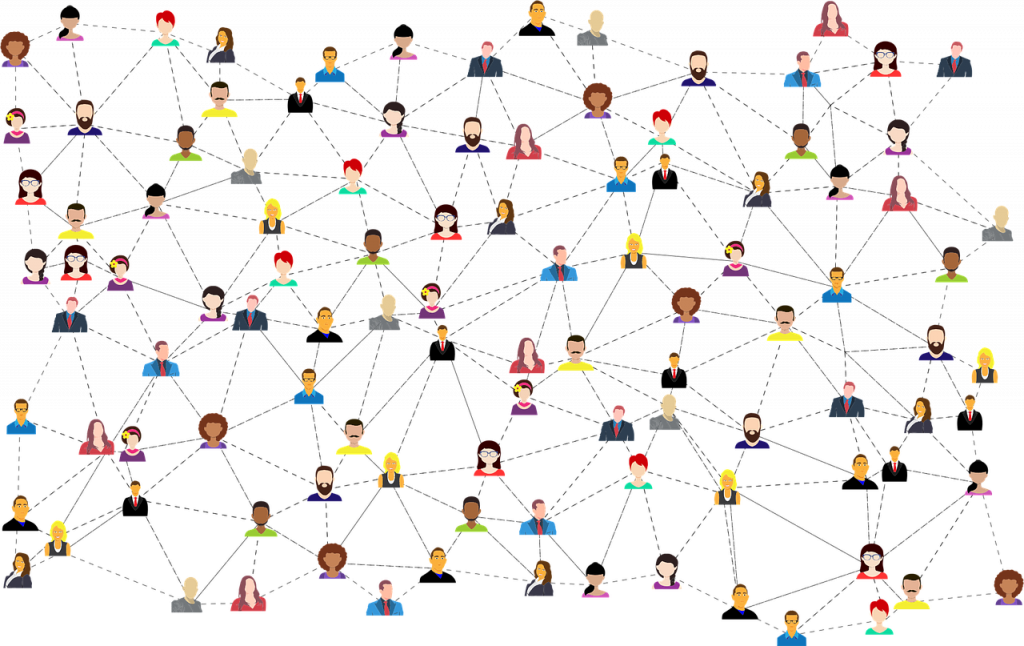
健康経営優良法人の認定を目指す場合は、「単発イベント」ではなく “仕組み化され、継続できる取り組み” であることが評価されます。
例えば、
- 「月1回の部署横断ランチ制度」
- 「年間2回の社内イベントを継続開催」
- 「定期的なありがとうメッセージの共有」
といった形で、制度やルールとして組み込むことが重要です。
無料でできる取り組み
「サンクスメッセージ(ありがとうカード)」制度
最も手軽に始められるのが、社員同士で感謝の気持ちを伝え合う「サンクスメッセージ制度」です。紙のカードをオフィス内に設置してもよいですし、社内メールやチャットツールを利用しても構いません。重要なのは「ありがとう」という言葉を形にして可視化することです。たとえば「昨日の資料作成を手伝ってくれてありがとう」「急な対応をしてもらって助かった」といった小さな感謝を言葉にするだけで、職場の雰囲気はぐっと柔らかくなります。そして、部門を越えたつながりが自然に生まれ、社員同士の信頼関係を深めることができます。コストをかけずに始められる点で、中小企業でも取り組みやすい方法といえるでしょう。
また、費用はかかりますが、サンクスメッセージ専用のサービスもあり、後ほどご紹介するありがとうポイントとの連携も可能です。HANDSやポムの樹など様々な企業がこの活動を行っています。まずは手軽な紙のカードから始めてみると良いでしょう。
少し手間がかかる取り組み
①飲食費補助制度
次に紹介するのは、部署を越えた交流を生み出すイベント飲食費補助制度です。サイボウズでは部門を超えたメンバーでイベントを開催する際、1人2,000円(税込)を上限に飲食費の補助が受けられる「イベン10」という制度を運用しています。業務に関係のないテーマでイベントを開催する時にも使えるので、多様で幅広いコミュニケーションの促進にも繋がっており、新卒入社メンバーとキャリア入社メンバーの交流会や、多拠点からの出張者の歓迎会などで活用されています。また、海外拠点からの出張者と懇親会をしたとき、1人3,000円(税込)を上限に飲食費の半額を補助してもらえる制度もあります。
こうした制度があると、社員は気兼ねなく他部署の人を誘いやすくなり、仕事上では話しづらいこともリラックスした雰囲気の中で共有できるようになります。
これらの交流を通して横のつながりを強化することは業務のスピード感を高めることにつながります。導入には多少のコストと運用ルールづくりが必要ですが、交流のきっかけを制度化することで社員の関係性が自然に深まり、組織全体のコミュニケーションを活性化させることができるでしょう。
②オンライン朝礼・シャッフル交流
近年のリモートワークの広がりに伴い、オンラインでのコミュニケーションをどう維持するかが課題になっています。そこで有効なのが「オンライン朝礼」や「シャッフル交流」です。これは、TeamsやZoomといったオンラインツールを用いて短時間の雑談タイムを設けたり、ランダムに組まれた社員同士で1対1の交流を行ったりする取り組みです。
オージャストではオンライン朝礼を行っています。オンライン朝礼にはコミュニケーションの活性化の他にも、情報共有できる・話す練習になる・始業時間に従業員がそろいやすくなるなどのメリットがあります。
運営には多少の時間とシステム整備が必要ですが、遠隔勤務が当たり前になりつつある今、企業規模を問わず取り入れやすい取り組みといえるでしょう。
大掛かりな取り組み
①「ありがとうポイント」制度
感謝の文化をさらに定着させたい場合には、「ありがとう」をポイント化して見える形にする「ありがとうポイント制度」が効果的です。社員同士が日常の中で感謝を感じたときにポイントを贈り合い、それを社内システム上で共有する仕組みです。単なる「ありがとう」ではなく、ポイントという数値で可視化されるため、感謝のやり取りが活発になりやすいのが特徴です。
株式会社TRUSTでは感謝の言葉を伝えるために「グッジョブカード」を使用しています。そして、メンバー同士で交換されたグッジョブカードを月に1回、人事部が回収して、各メンバーが渡した枚数と受け取った枚数をカウントし、枚数が多い人は人事評価に反映させています。これは他の複数の指標と組み合わせて評価を行い、給与アップにつなげています。単なる慣習でなく、このように制度化することで、2年以上運用を続けられているそうです。
このようにシステム導入や運営体制の構築が必要となるためコストはかかりますが、その分大きな効果が期待できます。
②社内イベント・合宿型コミュニケーション研修
最後に紹介するのは、全社を巻き込む大規模な取り組みである「社内イベント」や「合宿型研修」です。スポーツ大会や文化祭、1泊2日の合宿ワークショップなどを通じて、社員同士が仕事以外の場面で関わり合うことができます。普段は業務で接点のないメンバーが一緒に汗を流したり議論したりすることで、深い信頼関係や仲間意識が芽生えます。
アンファー株式会社では、創業25周年を迎えた年から毎年社内運動会を開催しています。企画には時間がかかりますが、外注も可能です。こうした取り組みは準備や予算の確保といったハードルがありますが、一度実施すれば強いインパクトを残し、社員のロイヤリティ向上や組織全体の団結力を高める効果が期待できます。
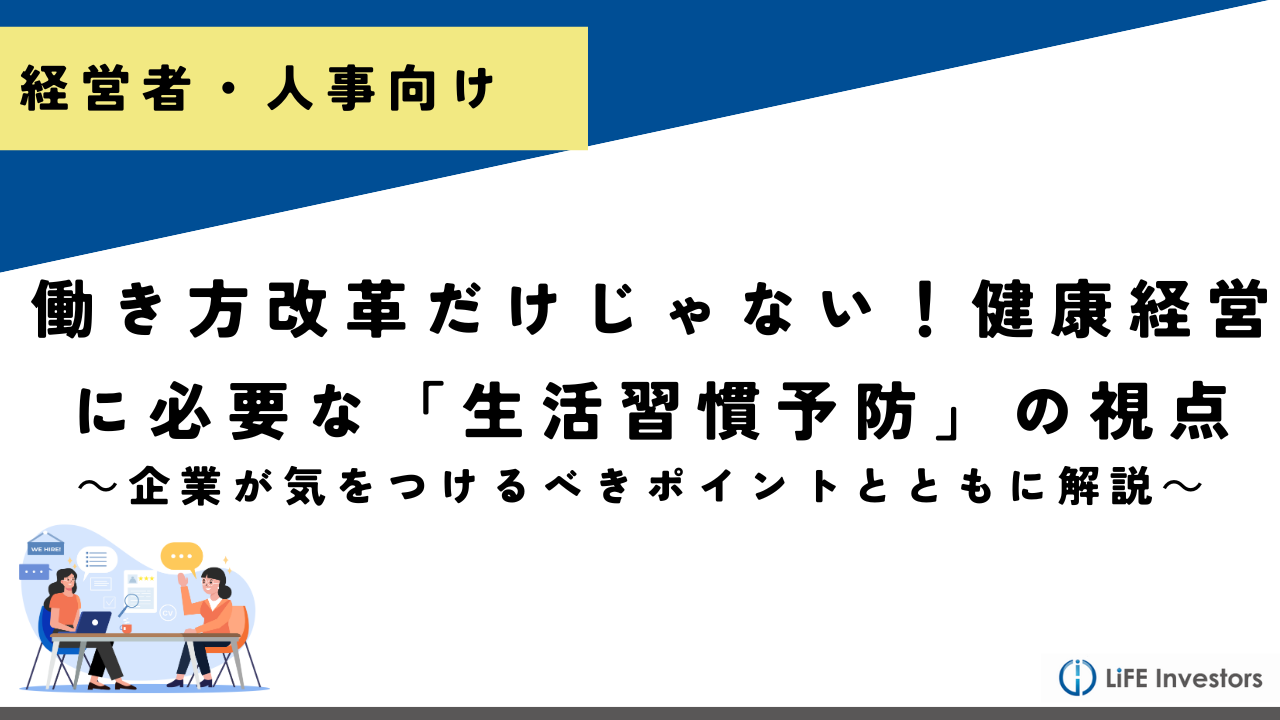
まとめ
健康経営における「コミュニケーションの促進」は、大掛かりなイベントから、ありがとうカードのような小さな工夫まで、多様な形で実現できます。大切なのは、企業の規模や文化に合った方法を無理なく導入し、継続することです。
まずは無料で始められる感謝の共有から、小規模な補助制度やオンライン施策へ、さらに余裕があればポイント制度や大型イベントへと段階的に取り入れるのが効果的です。小さな一歩が、やがて健康経営優良法人の認定につながる大きな成果へと育っていきます。
健康経営の取り組みを専門家と一緒に進めたい方へ
コミュニケーション促進の仕組みを導入しても、うまく浸透させるには専門的な視点が必要になることがあります。特に「健康経営優良法人の認定を取りたい」「産業医と連携しながら職場改善を進めたい」と考えている法人様にとっては、外部のサポートを受けることが大きな力になります。
ライフインベスターズでは、産業医・保健師の紹介を通じて健康経営の支援を行っています。
- 健康経営優良法人の認定を目指す企業向けの無料相談
- 導入事例や取り組み方がわかる資料請求
これらを通じて、企業の成長と従業員の健康を両立させるお手伝いをしています。
健康経営を次のステージへと進めたい方は、ぜひ一度ライフインベスターズにご相談ください。
【参考文献】
コミュニケーション方法 | 採用情報 | サイボウズ株式会社
‘ありがとう’の数だけ「人事評価」につながる!社内の感謝を「見える化」する、5つの効果 | リクナビNEXTジャーナル